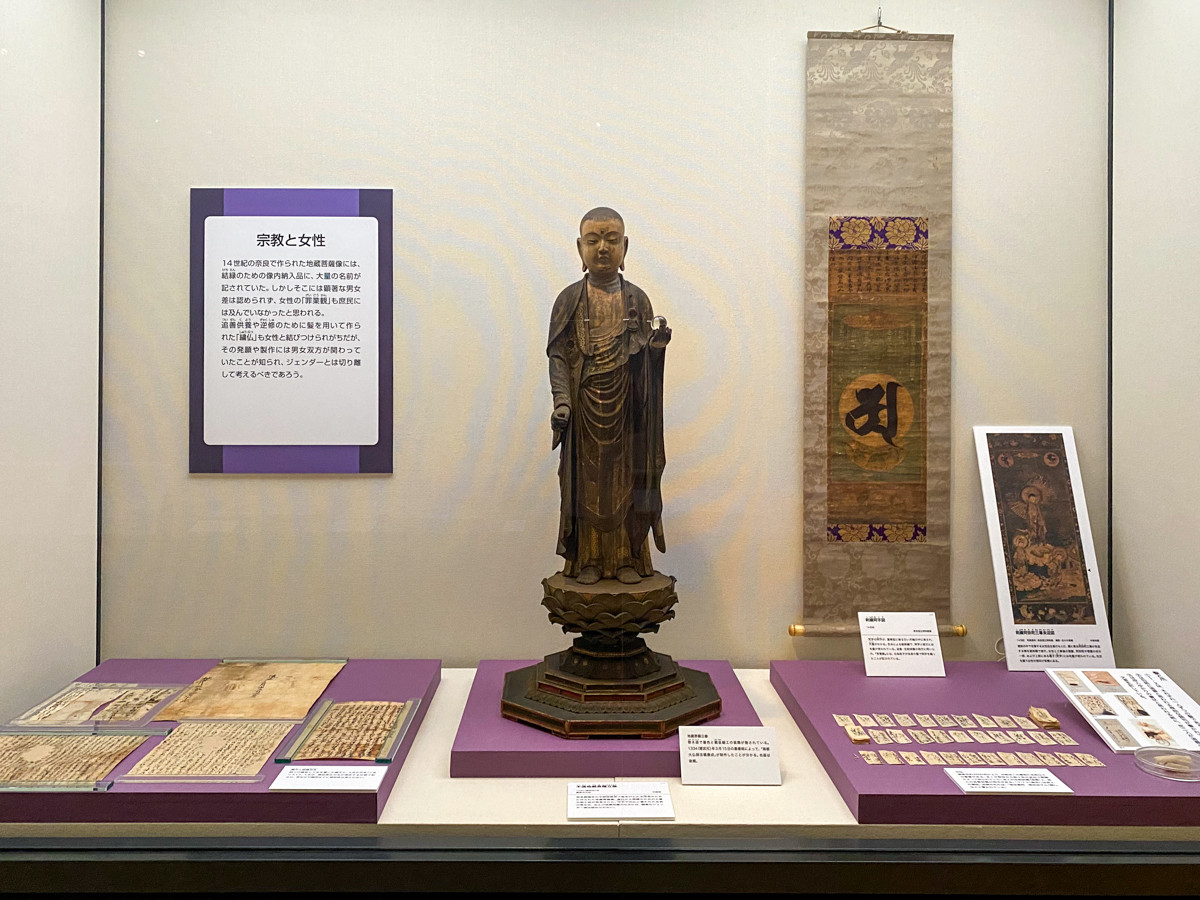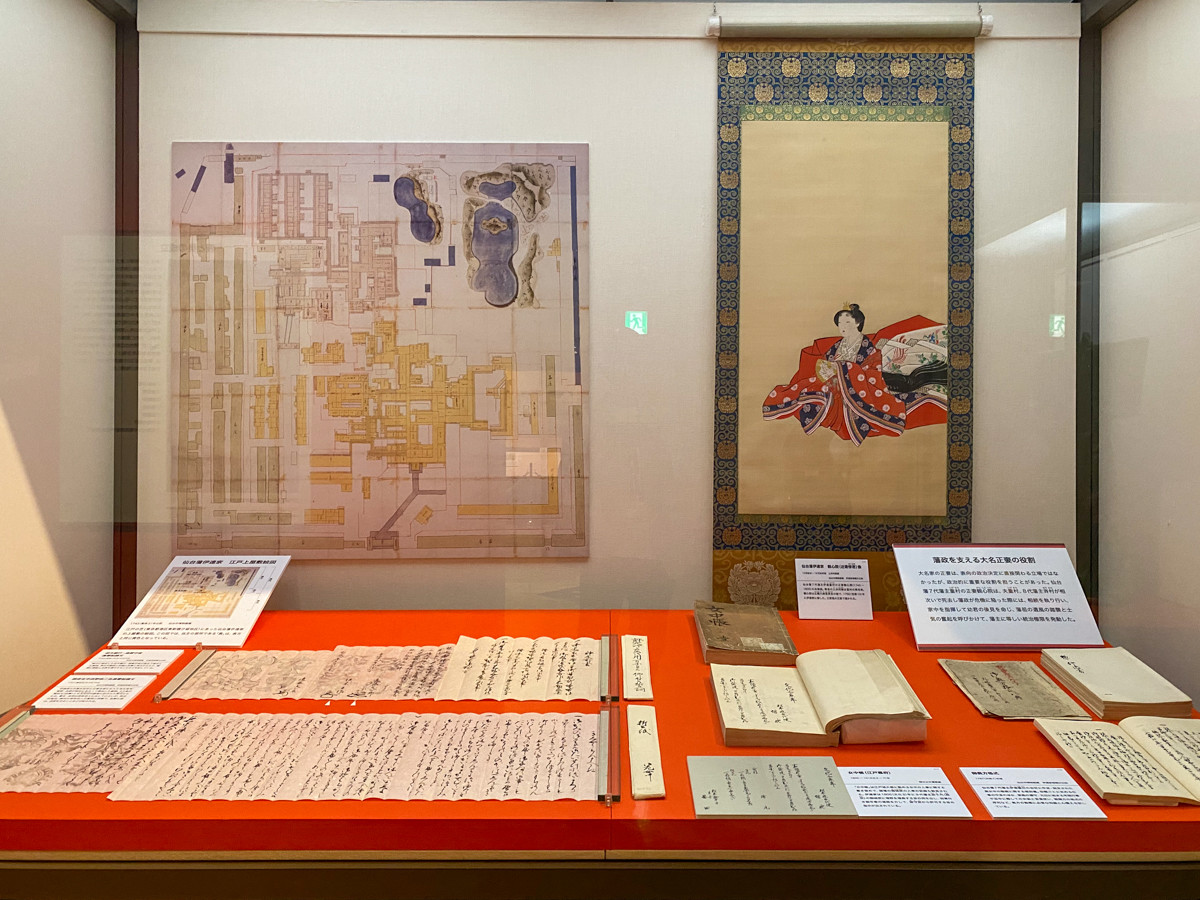IM
レポート
レポート
企画展示「性差(ジェンダー)の日本史」
国立歴史民俗博物館 | 千葉県
男女を区分するのはなぜ?ジェンダーの成り立ちとその変化を明らかに
女性の王や官僚が当たり前だった古代から、女性が排除された明治の近代へ
買売春の歴史も考察、社会の一員だった遊女集団が抑圧された隷属関係に
2
| 会場 | 国立歴史民俗博物館 |
| 会期 |
2020年10月6日(火)〜12月6日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 9時30分~16時30分(入館は16時00分まで) ※開館日・開館時間を変更する場合があります。 |
| 休館日 | 毎週月曜日(休日にあたる場合は開館し、翌日休館) |
| 住所 | 〒285-8502 千葉県佐倉市城内町117 |
| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |
| 公式サイト | https://www.rekihaku.ac.jp |
| 料金 | 一般:1000円 / 大学生:500円 ※総合展示もあわせてご覧になれます。 ※高校生以下は入館料無料です。 ※高校生及び大学生の方は、学生証等を提示してください。(専門学校生など高校生及び大学生に相当する生徒、学生も同様です) ※障がい者手帳等保持者は手帳提示により、介助者と共に入館が無料です。 ※半券の提示で当日に限りくらしの植物苑にご入場できます。 |
| 展覧会詳細 | 「性差(ジェンダー)の日本史」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年4月25日
「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」
2025年4月25日
ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」
2025年4月25日
88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集
[京都精華大学ギャラリーTerra-S]
京都府
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)