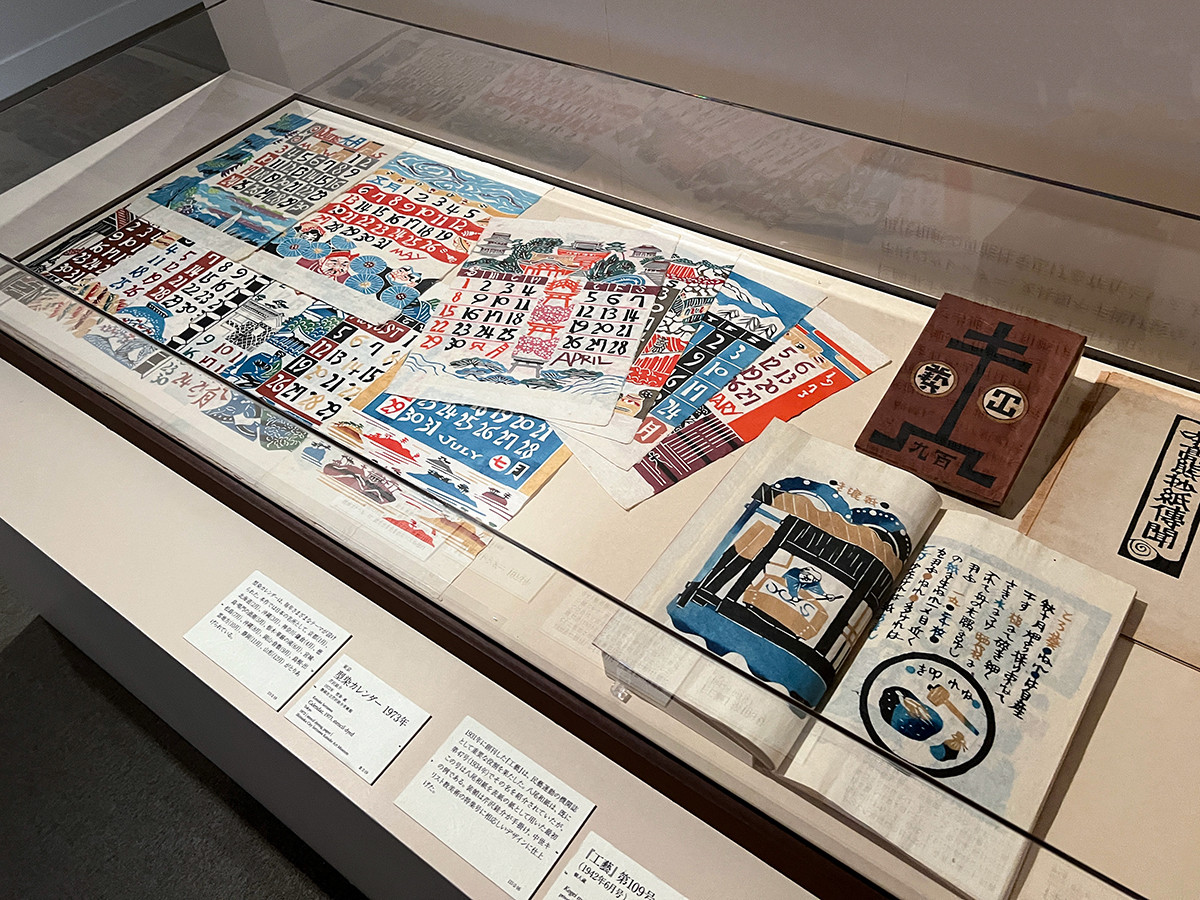IM
レポート
レポート
民藝 MINGEI―美は暮らしのなかにある
世田谷美術館 | 東京都
柳宗悦が説いた「民藝」とはなにか。「衣・食・住」をテーマにひも解く
「これからの民藝スタイル」を提案する、インスタレーション作品も展示
民藝ファンには憧れの老舗の名品・人気の工房が集結した特設ショップも
6
第Ⅱ章:暮らしのなかの民藝
第Ⅱ章:暮らしのなかの民藝
第Ⅱ章:暮らしのなかの民藝
第Ⅲ章: ひろがる民藝 「小鹿田焼」
特設ショップ
特設ショップ
| 会場 | 世田谷美術館 |
| 会期 |
2024年4月24日(水)〜6月30日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~18:00(入場は17:30まで) |
| 休館日 | 毎週月曜日 ※4月29日(月・祝)、5月6日(月・振休)は開館、5月7日(火)は休館 |
| 住所 | 〒157-0075 東京都世田谷区砧公園1-2 |
| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |
| 公式サイト | https://mingei-kurashi.exhibit.jp/ |
| 展覧会詳細 | 「民藝 MINGEI ―美は暮らしのなかにある」 詳細情報 |
大阪府
2023年7月8日(土)〜9月18日(月)
大阪中之島美術館
会期終了
展覧会の詳細はこちら
広島県
2024年2月10日(土)〜3月24日(日)
東広島市立美術館
会期終了
展覧会の詳細はこちら
東京都
2024年4月24日(水)〜6月30日(日)
世田谷美術館
会期終了
展覧会の詳細はこちら
愛知県
2024年10月5日(土)〜12月22日(日)
名古屋市美術館
会期終了
展覧会の詳細はこちら
福岡県
2025年2月8日(土)〜4月6日(日)
福岡市博物館
会期終了
展覧会の詳細はこちら
千葉県
2025年4月22日(火)〜6月29日(日)
千葉県立美術館
開催中[あと65日]
展覧会の詳細はこちら
おすすめレポート
ニュース
2025年4月25日
「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」
2025年4月25日
ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」
2025年4月25日
88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集
[京都精華大学ギャラリーTerra-S]
京都府
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)