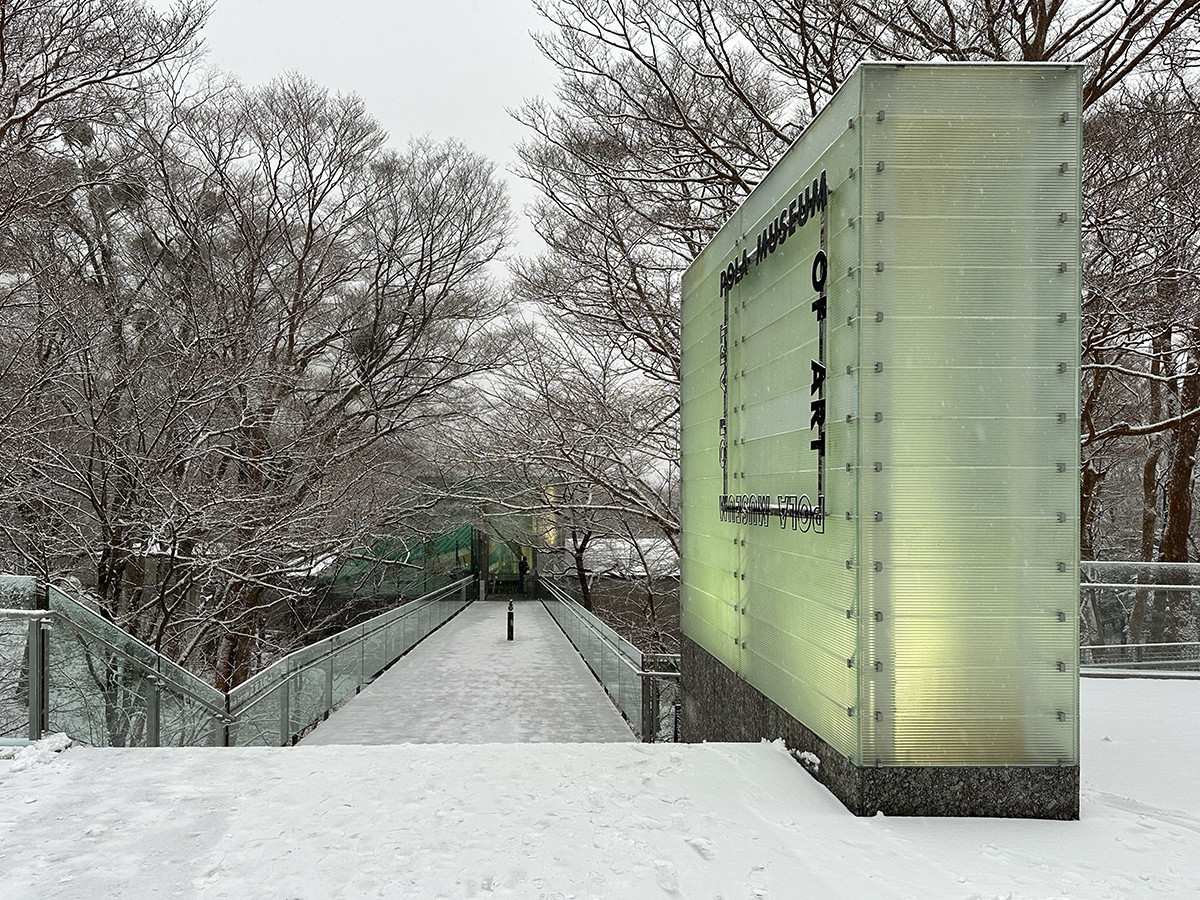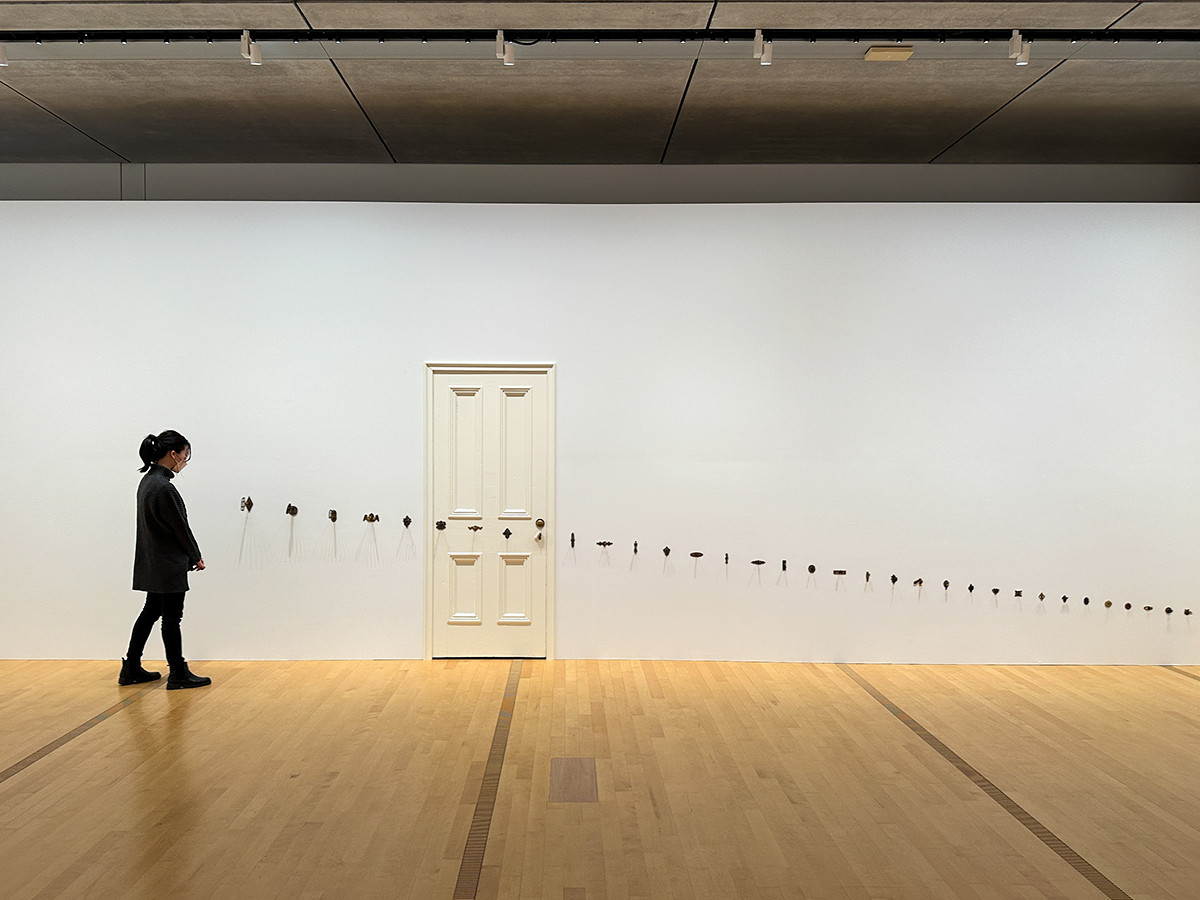IM
レポート
レポート
部屋のみる夢 ― ボナールからティルマンス、現代の作家まで
ポーラ美術館 | 神奈川県
コロナ禍で移動が制限され、誰もが多くの時間を過ごした「部屋」がテーマ
アンリ・マティス、ピエール・ボナールなど、19世紀から現代までの約50点
現代を代表する草間彌生とヴォルフガング・ティルマンスは新収蔵作品も
1
ポーラ美術館「部屋のみる夢 ― ボナールからティルマンス、現代の作家まで」会場入口
(左から)エドゥアール・ヴュイヤール《画家のアトリエ》1915年 ポーラ美術館 / エドゥアール・ヴュイヤール《服を脱ぐモデル、マルゼルブ大通り》1909年頃 ポーラ美術館
ピエール・ボナール《地中海の庭》1917-1918年 ポーラ美術館
草間彌生《蝶》2001年 個人蔵
| 会場 | ポーラ美術館 |
| 会期 |
2023年1月28日(土)〜7月2日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 9:00~17:00(最終入館16:30) |
| 休館日 | 会期中無休 |
| 住所 | 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285 |
| 電話 | 0460-84-2111(代表) |
| 公式サイト | https://www.polamuseum.or.jp/ |
| 料金 | 大人1,800円 シニア割引(65歳以上)1,600円 大学・高校生1,300円 |
| 展覧会詳細 | 「部屋のみる夢 ― ボナールからティルマンス、現代の作家まで」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年4月18日
横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集
[京都精華大学ギャラリーTerra-S]
京都府
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)