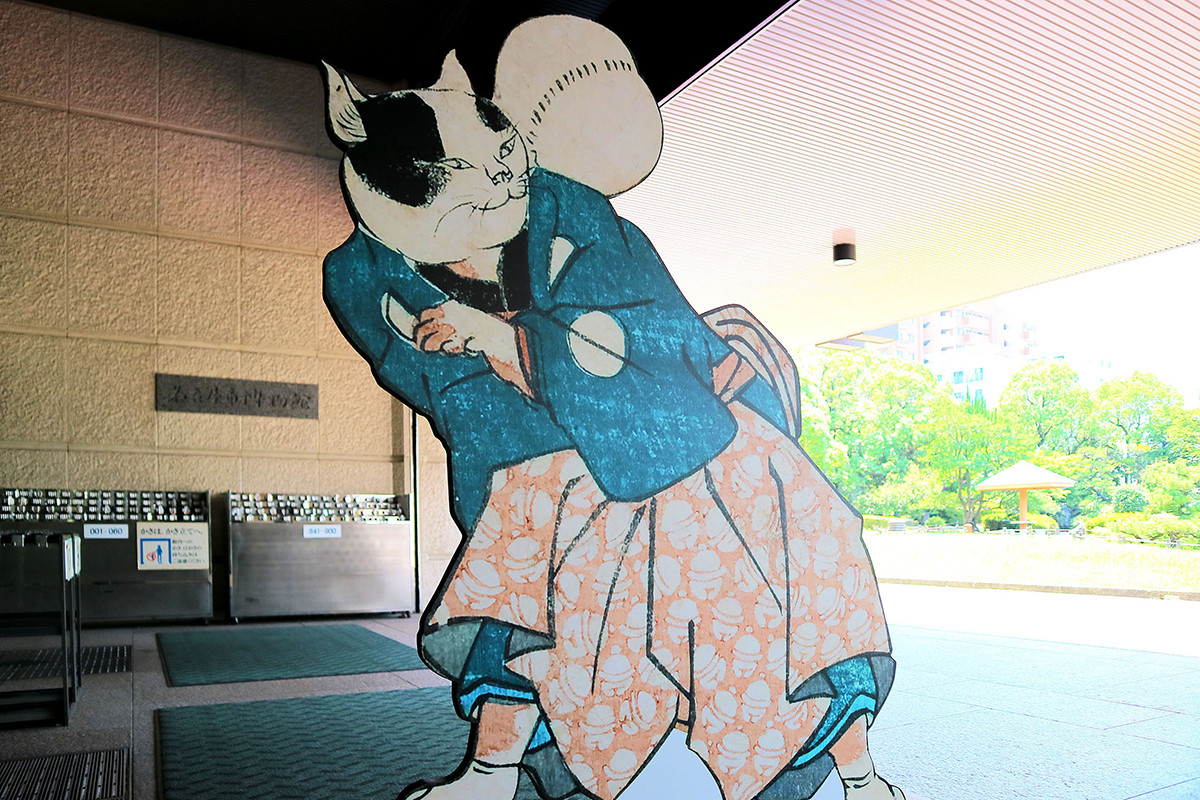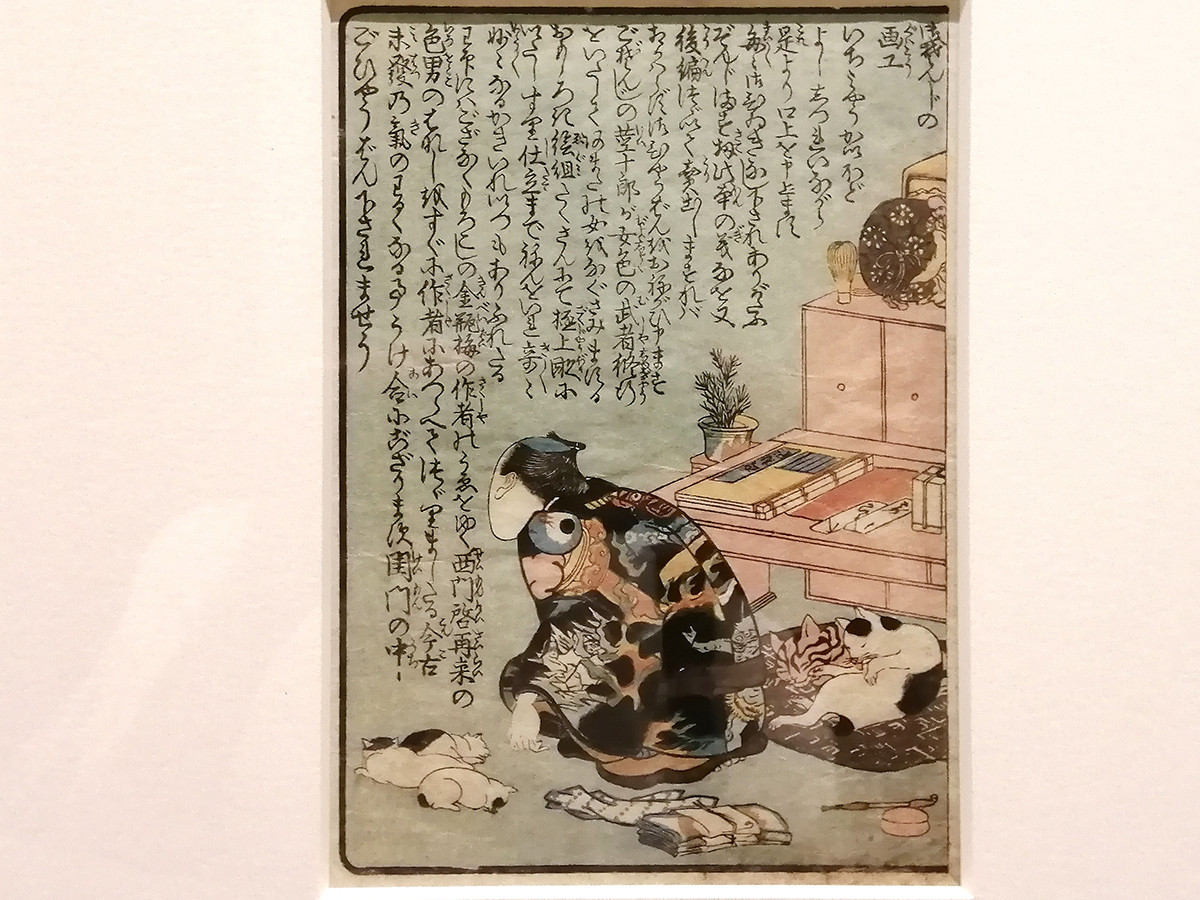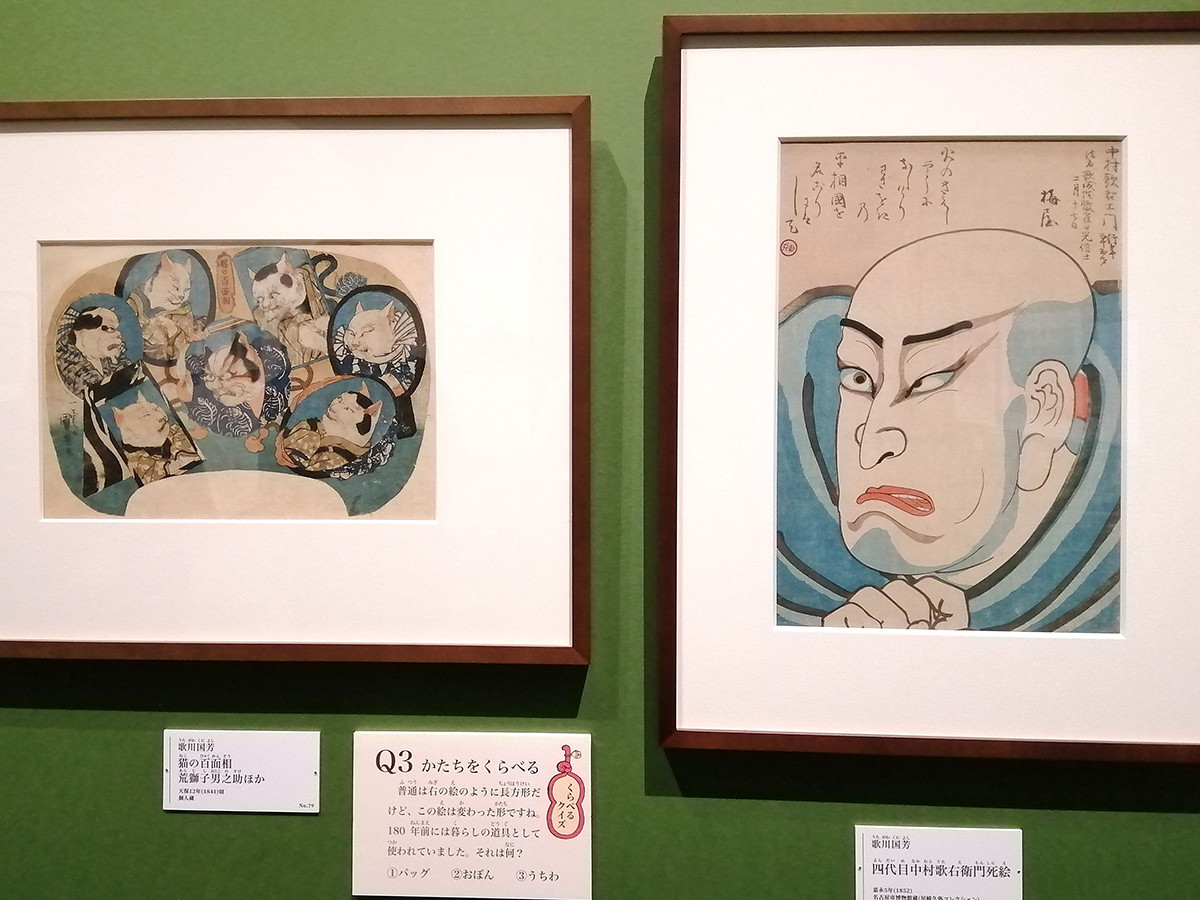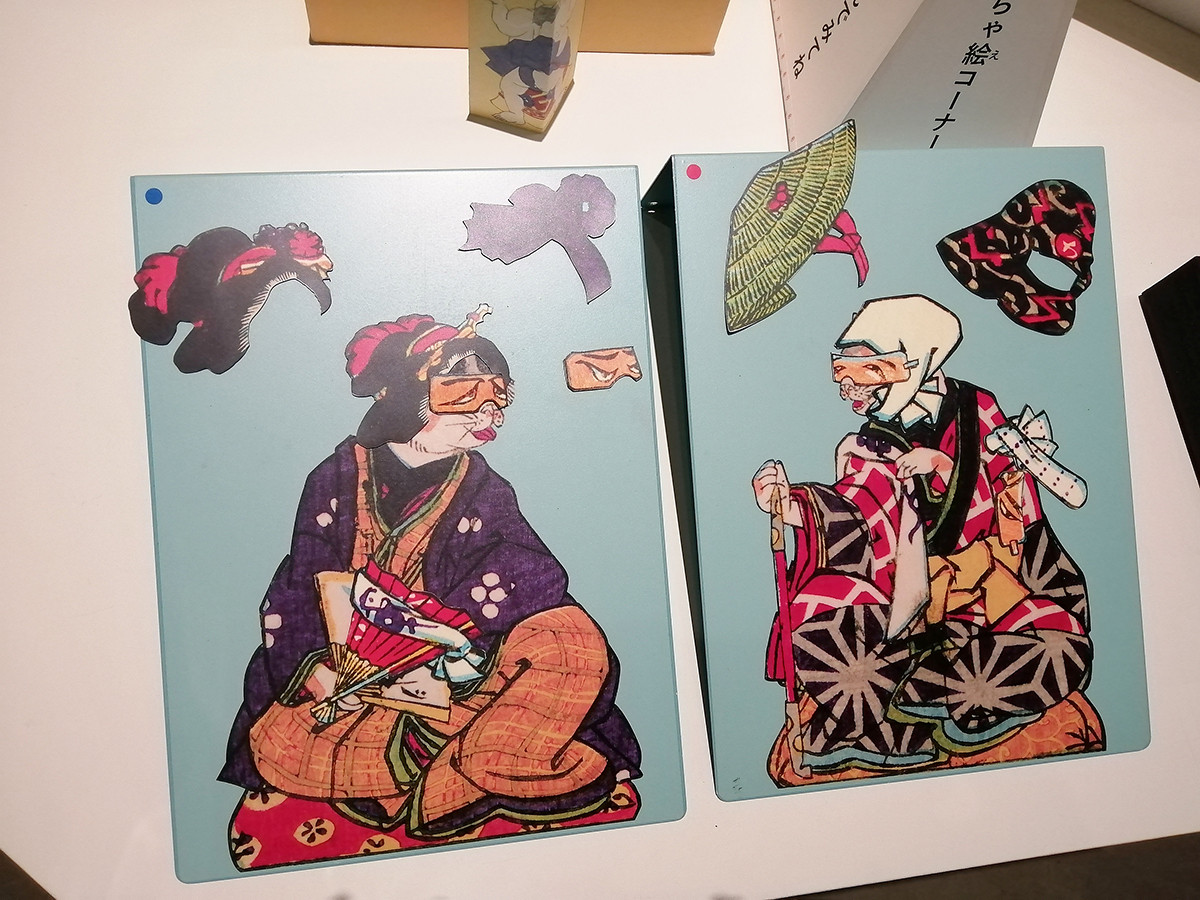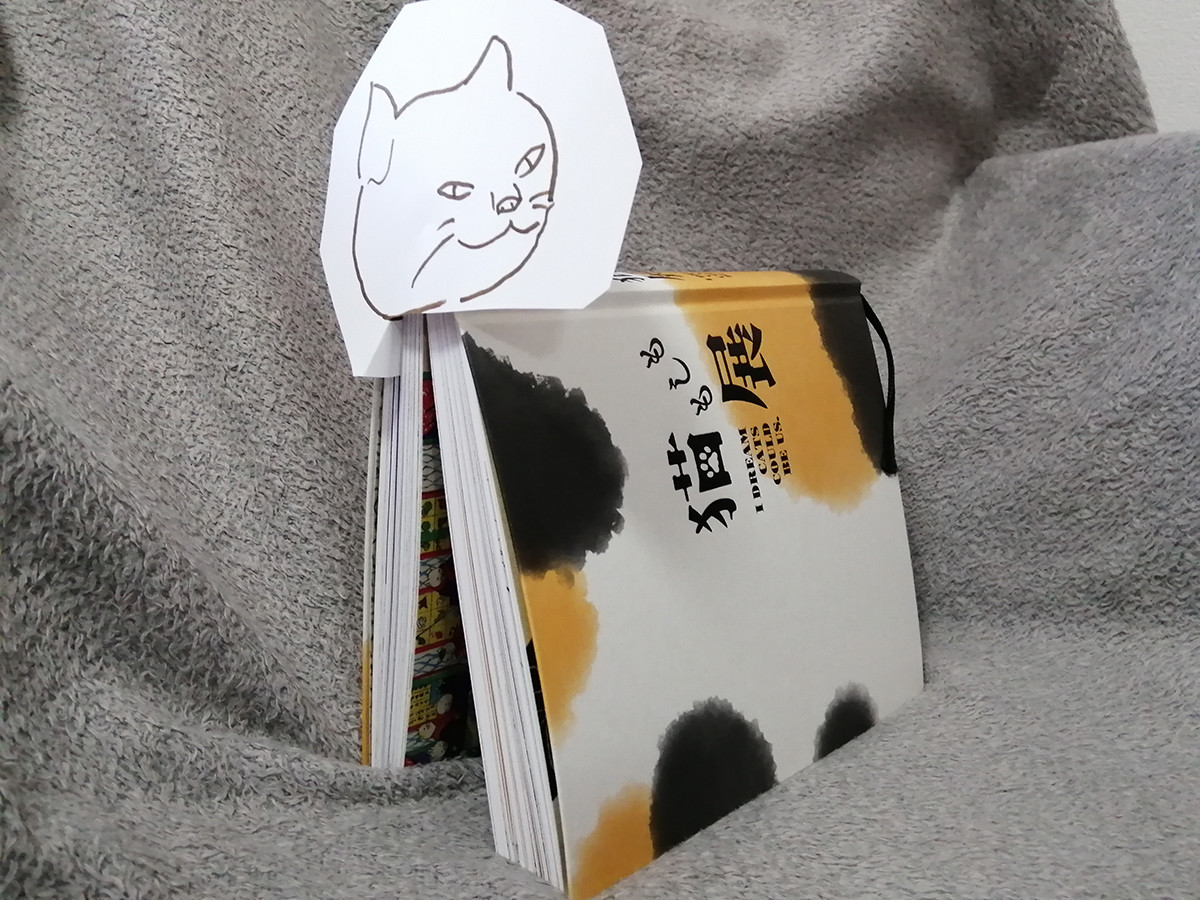読者
レポート
レポート
もしも猫展
名古屋市博物館 | 愛知県
| 会場 | 名古屋市博物館 |
| 会期 |
2022年7月2日(土)〜8月21日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 9時30分~17時(入場は16時30分まで) |
| 休館日 | 7月4日、11日、19日、25日、26日、8月1日、8日 |
| 住所 | 〒467-0806 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通1-27-1 |
| 電話 | 052-853-2655 |
| 公式サイト | https://www.ctv.co.jp/nekoten/ |
| 料金 | 一般:1,600円(1,400円) 高大生:1,000円(800円) 小中生:500円(300円) ※( )内は前売および20名以上の団体料金。 |
| 展覧会詳細 | 「特別展 もしも猫展」 詳細情報 |
1
読者レポーターのご紹介
ぴよまるこ
美術関連の仕事に就いており、絵画から陶芸までさまざまな作品に接し「はあ~」「ほお~」と感動する日々を過ごしています。
アートを観る楽しさ、展覧会の臨場感を少しでもお伝えできればと思っています。
おすすめレポート
ニュース
2025年4月25日
「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」
2025年4月25日
ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」
2025年4月25日
88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集
[京都精華大学ギャラリーTerra-S]
京都府
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)