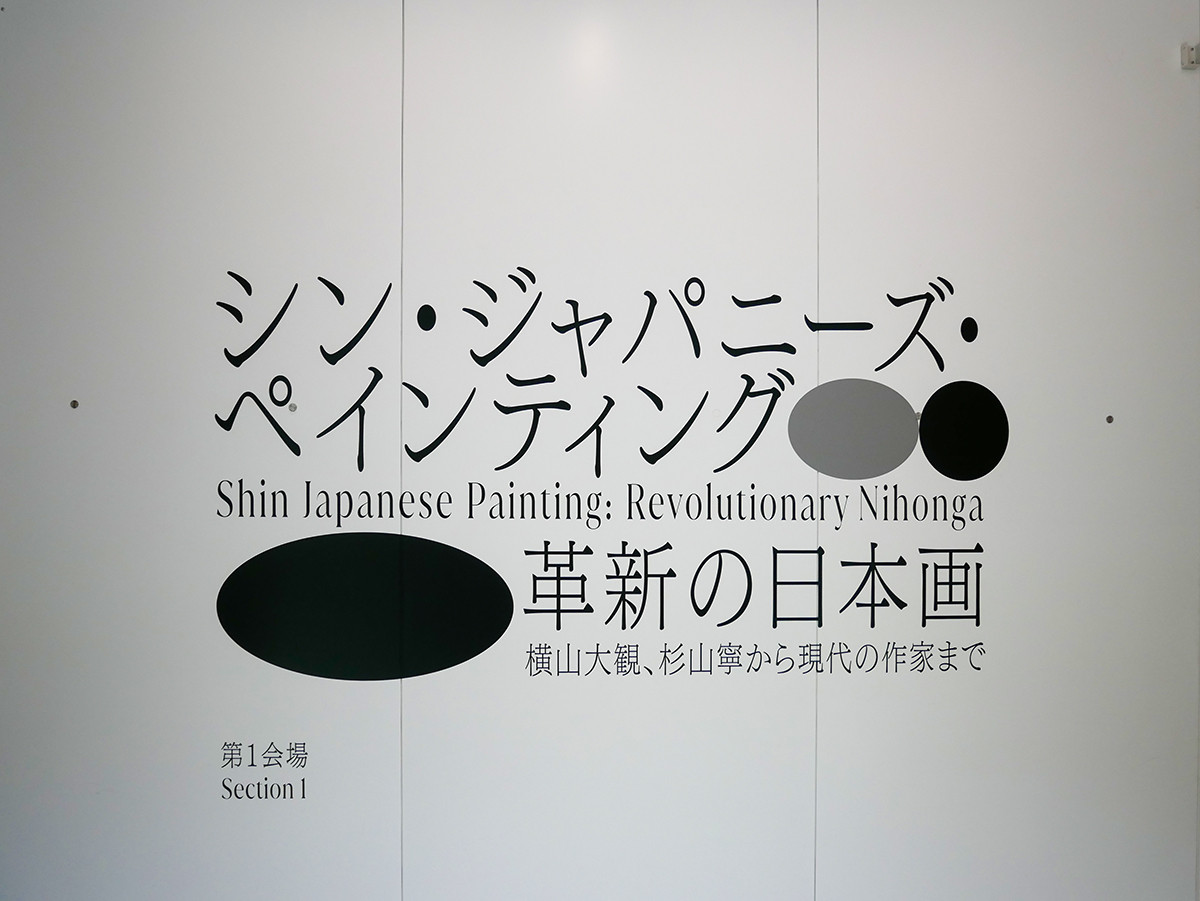読者
レポート
レポート
シン・ジャパニーズ・ペインティング
ポーラ美術館 | 神奈川県
| 会場 | ポーラ美術館 |
| 会期 |
2023年7月15日(土)〜12月3日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |
| 休館日 | 会期中無休 |
| 住所 | 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285 |
| 電話 | 0460-84-2111(代表) |
| 展覧会詳細 | 「シン・ジャパニーズ・ペインティング 」 詳細情報 |
2
読者レポーターのご紹介
芝
休日になると首都圏近郊の美術館・博物館を訪ね回っています。
下記noteでも美術館巡りの記録を書き溜めているので、よかったら覗いてみてください。
https://note.com/shiba_tabi
読者レポーター募集中!
あなたの目線でミュージアムや展覧会をレポートしてみませんか? → 詳しくはこちら
下記noteでも美術館巡りの記録を書き溜めているので、よかったら覗いてみてください。
https://note.com/shiba_tabi
読者レポーター募集中!
あなたの目線でミュージアムや展覧会をレポートしてみませんか? → 詳しくはこちら
おすすめレポート
ニュース
2025年4月25日
「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」
2025年4月25日
ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」
2025年4月25日
88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
京都精華大学ギャラリーTerra-S アシスタント募集
[京都精華大学ギャラリーTerra-S]
京都府
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)