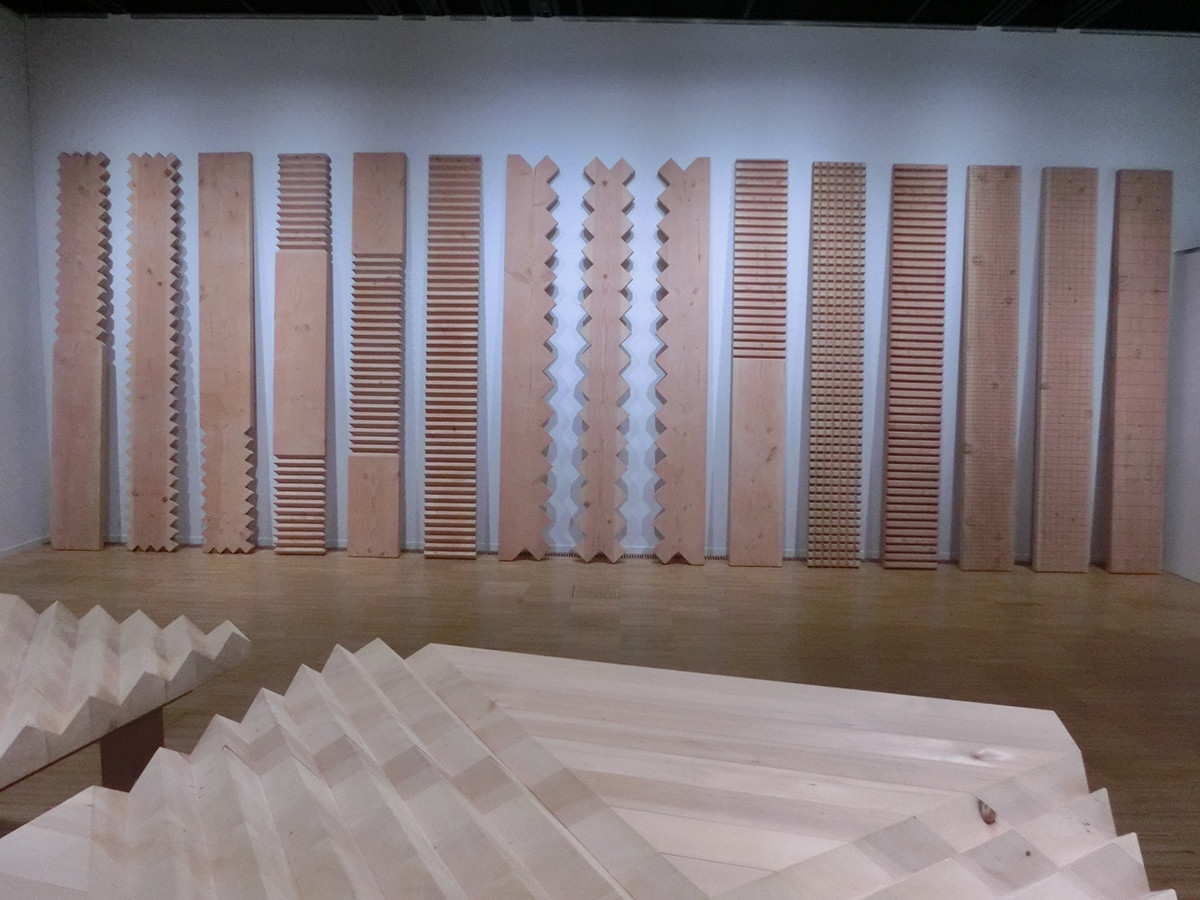読者
レポート
レポート
「表面」が語るモノ ― 宝塚市立文化芸術センター「小清水漸の彫刻」(読者レポート)
宝塚市立文化芸術センター | 兵庫県
| 会場 | 宝塚市立文化芸術センター |
| 会期 |
2024年9月14日(土)〜10月15日(火)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~18:00(メインギャラリーへの入場受付は17:30まで) |
| 休館日 | 水曜休館(祝日は開館) |
| 住所 | 〒665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町7-64 |
| 電話 | 0797-62-6800 |
| 公式サイト | https://takarazuka-arts-center.jp/ |
| 料金 | 一般(高校生以上) 1,000円(メインギャラリーのみ、庭園エリアは無料) ※中学生以下無料 ※障がい者手帳ご提示でご本人様、付添の方1名まで無料 ※2024年度パートナー特典対象 |
| 展覧会詳細 | 「小清水漸の彫刻 1969~2024・雲のひまの舟」 詳細情報 |
0
読者レポーターのご紹介
田邉めぐみ
フランス中世写本画を専門とする美術史家。様々な時代や地域で制作された作品が、展示される場に応じてどのような顔をみせるのか。「展示される作品」と「作品を展示する場」との関係を考えながらレポートしてゆきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
おすすめレポート
ニュース
2025年4月18日
横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入
2025年4月18日
日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」
2025年4月18日
開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」
2025年4月15日
ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集
[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)