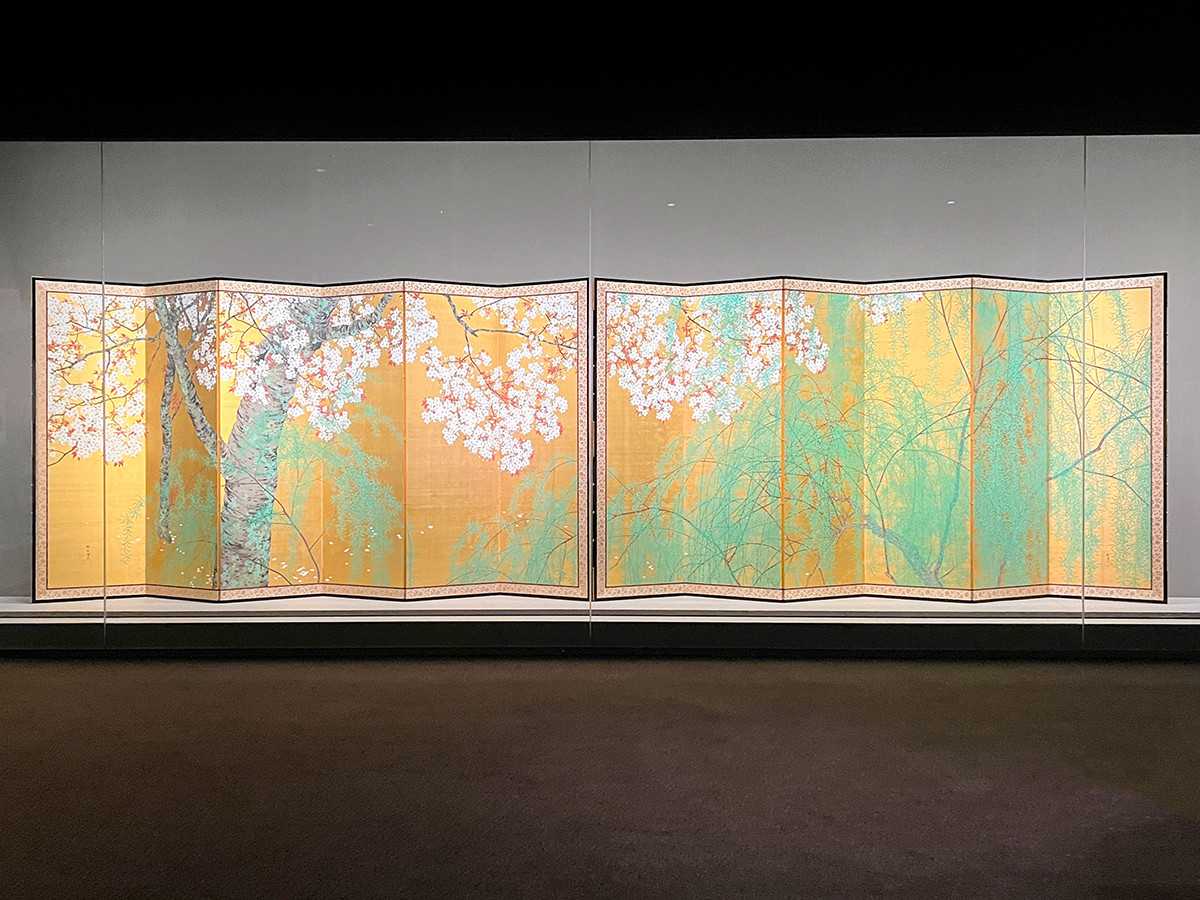IM
レポート
レポート
ライトアップ木島櫻谷 ― 四季連作大屛風と沁みる生写し
泉屋博古館東京 | 東京都
筆跡を油彩画の様に立体的にみえる筆触に挑戦し、“技巧派”と称された櫻谷
住友家本邸を飾るために描かれた、木島櫻谷の「四季連作屏風」を全点公開
京都で生まれた円山四条派の代表的な画家たちによる、花鳥画表現もならぶ
3
木島櫻谷《燕子花図》大正6年(1917)泉屋博古館東京
木島櫻谷《竹林白鶴》大正12年(1923)泉屋博古館東京
木島櫻谷《柳桜図》(部分)大正6年(1917)泉屋博古館東京
木島櫻谷《雪中梅花》(部分)大正7年(1918)泉屋博古館東京
第3章「櫻谷の動物たち、どこかヒューマンな。」
木島櫻谷《写生帖》明治時代(19-20世紀)櫻谷文庫
| 会場 | 泉屋博古館東京 |
| 会期 |
2024年3月16日(土)〜5月12日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 11:00~18:00 ※金曜日は19:00まで開館 ※入館は閉館の30分前まで |
| 休館日 | 月曜日、4/30・5/7(火)(4/29、5/6は開館) |
| 住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木1-5-1 |
| 電話 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |
| 公式サイト | https://sen-oku.or.jp/tokyo/ |
| 料金 | 一般1,000円(800円)、高大生600円(500円)、中学生以下無料 ※20名様以上の団体は( )内の割引料金 ※障がい者手帳等ご呈示の方はご本人および同伴者1名まで無料 |
| 展覧会詳細 | 「ライトアップ木島櫻谷 ― 四季連作大屛風と沁みる生写し」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年4月18日
横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入
2025年4月18日
日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」
2025年4月18日
開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」
2025年4月15日
ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集
[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)