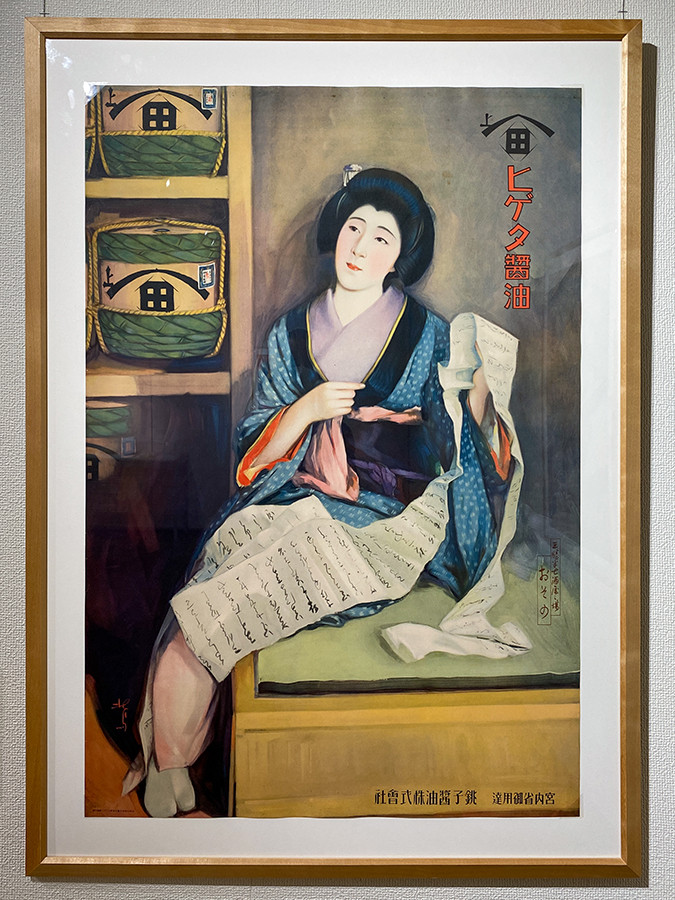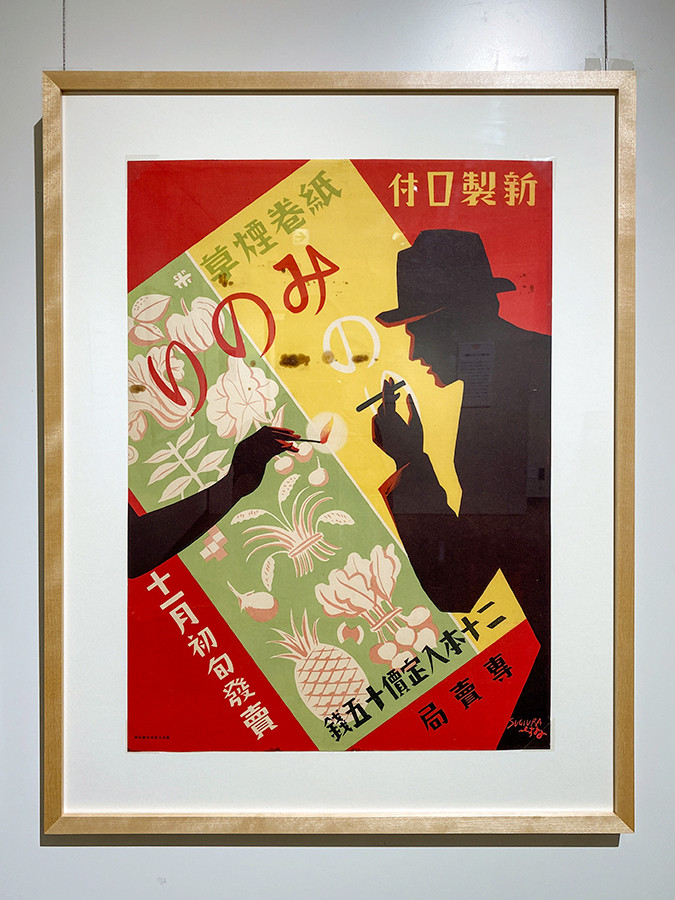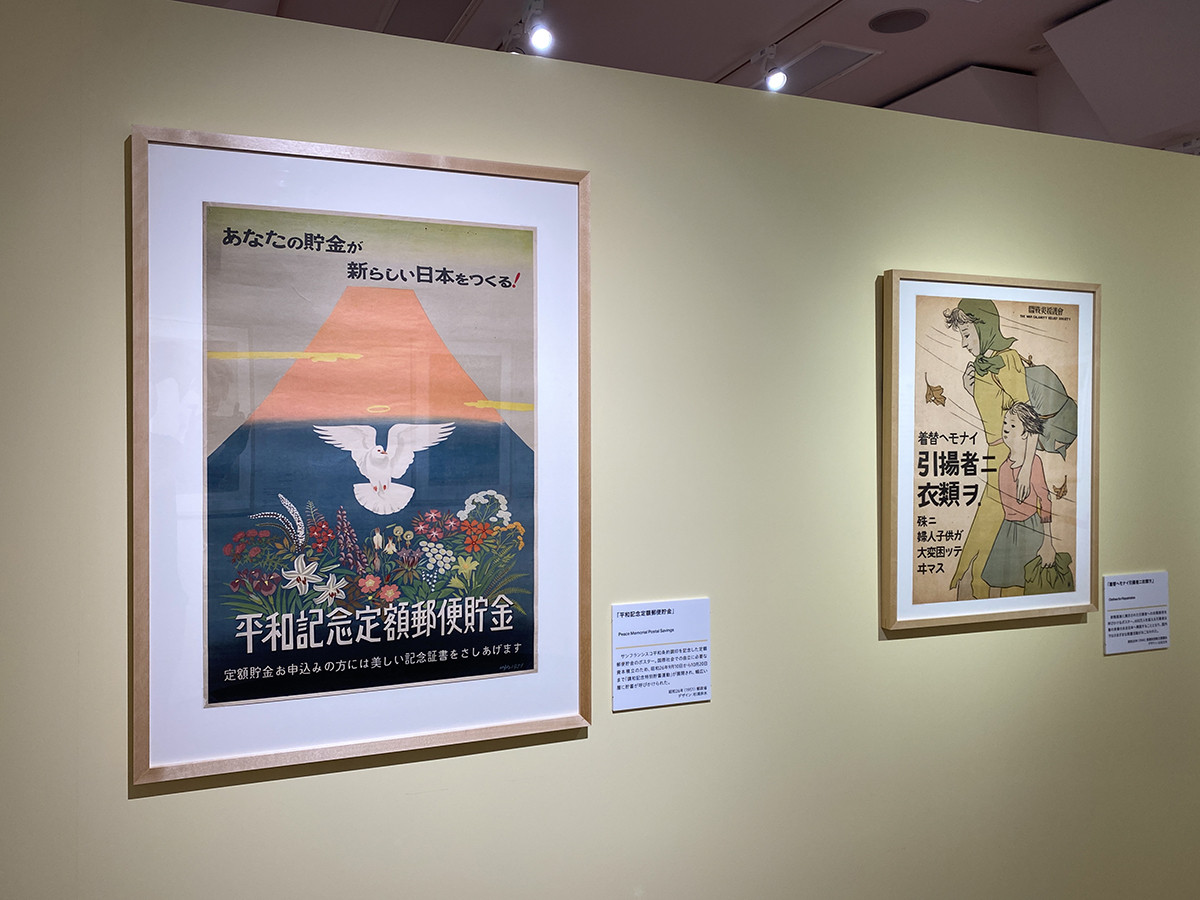IM
レポート
レポート
ポスターのちから
昭和館 | 東京都
デザインの変遷に着目して昭和期におけるポスター制作とデザイナーを紹介
戦時体制の強化で国策宣伝に使われたポスター、戦後は募金の呼びかけなど
目玉は1964年の東京パラリンピックの海外用公式ポスター、本展で初公開!
2
「月星編上靴」昭和10年(1935)デザイン:多田北烏
昭和館「ポスターのちから」会場風景
(左から)原画「共同募金・赤十字募金」昭和23年(1948)7月 デザイン:髙橋春人 / 「赤十字愛の献血運動」昭和38年(1963)デザイン:髙橋春人
昭和館「ポスターのちから」会場風景
| 会場 | 昭和館 |
| 会期 |
2021年7月17日(土)〜9月5日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 10時~13時30分(入館は13時まで) 14時~17時30分(入館は17時まで) ※13時30分~14時の間は館内清掃のため入館できません。 |
| 休館日 | 毎週月曜日(8月9日は開館、10日は休館) |
| 住所 | 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-1 |
| 電話 | 03-3222-2577 |
| 公式サイト | https://www.showakan.go.jp/ |
| 料金 | 無料 ※常設展示室は有料 |
| 展覧会詳細 | 「ポスターのちから」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年4月28日
鬼のものがたり、ここに始まる ― サントリー美術館「酒呑童子ビギンズ」
2025年4月25日
「太陽の塔」の裏にあった、もうひとつの物語 ― 企画展「岡本太郎と太陽の塔」
2025年4月25日
ゴールデンウイーク、渋谷に恐竜が出現! ― 「DINO SAFARI 2025」
2025年4月25日
88歳、横尾忠則が放つ新たな絵の流れ ― 世田谷美術館「横尾忠則 連画の河」
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
学生大歓迎!【アルバイト】名古屋市港防災センター 運営・接客/イベント業務スタッフ 募集!
[名古屋市港区港町1-12-20(名古屋市港防災センター)]
愛知県
国⽴国際美術館 研究補佐員(情報資料室)募集
[国立国際美術館]
大阪府
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)