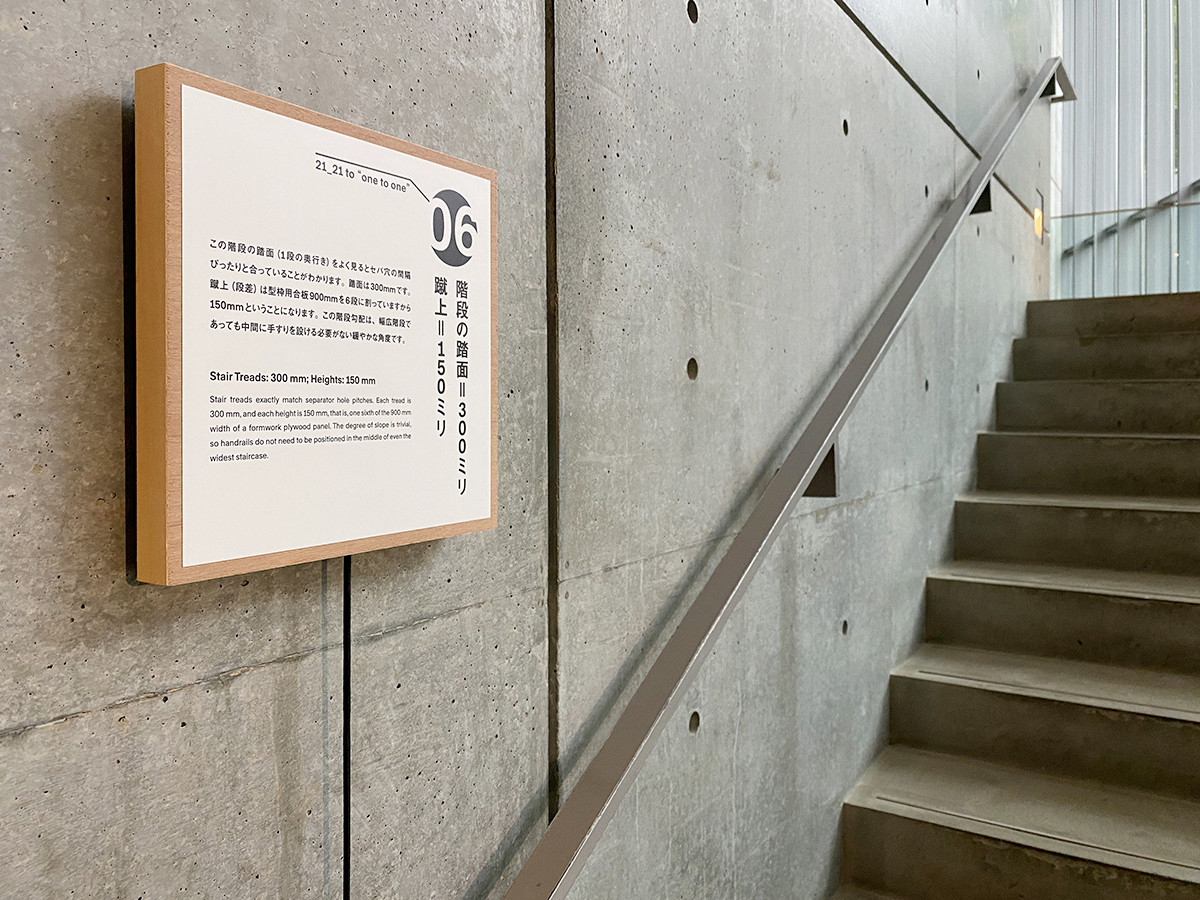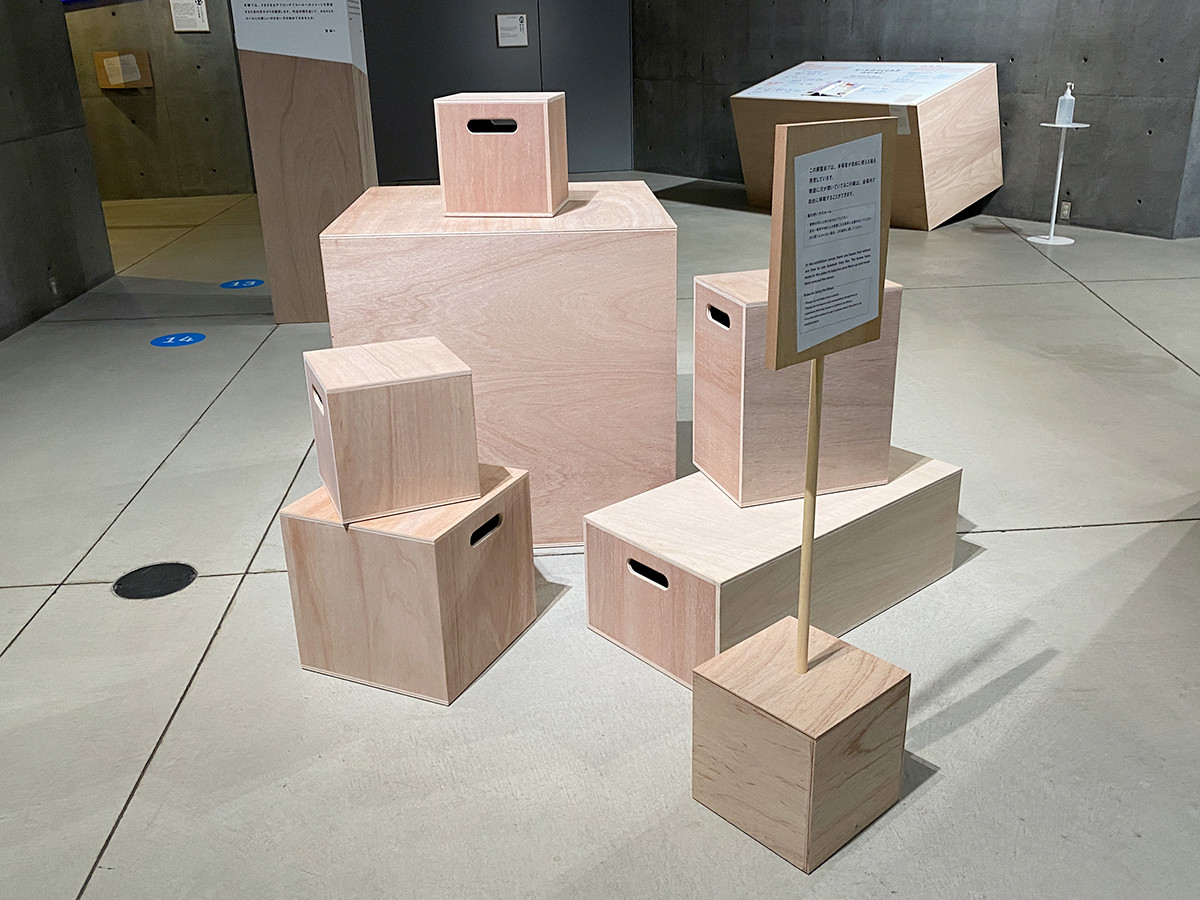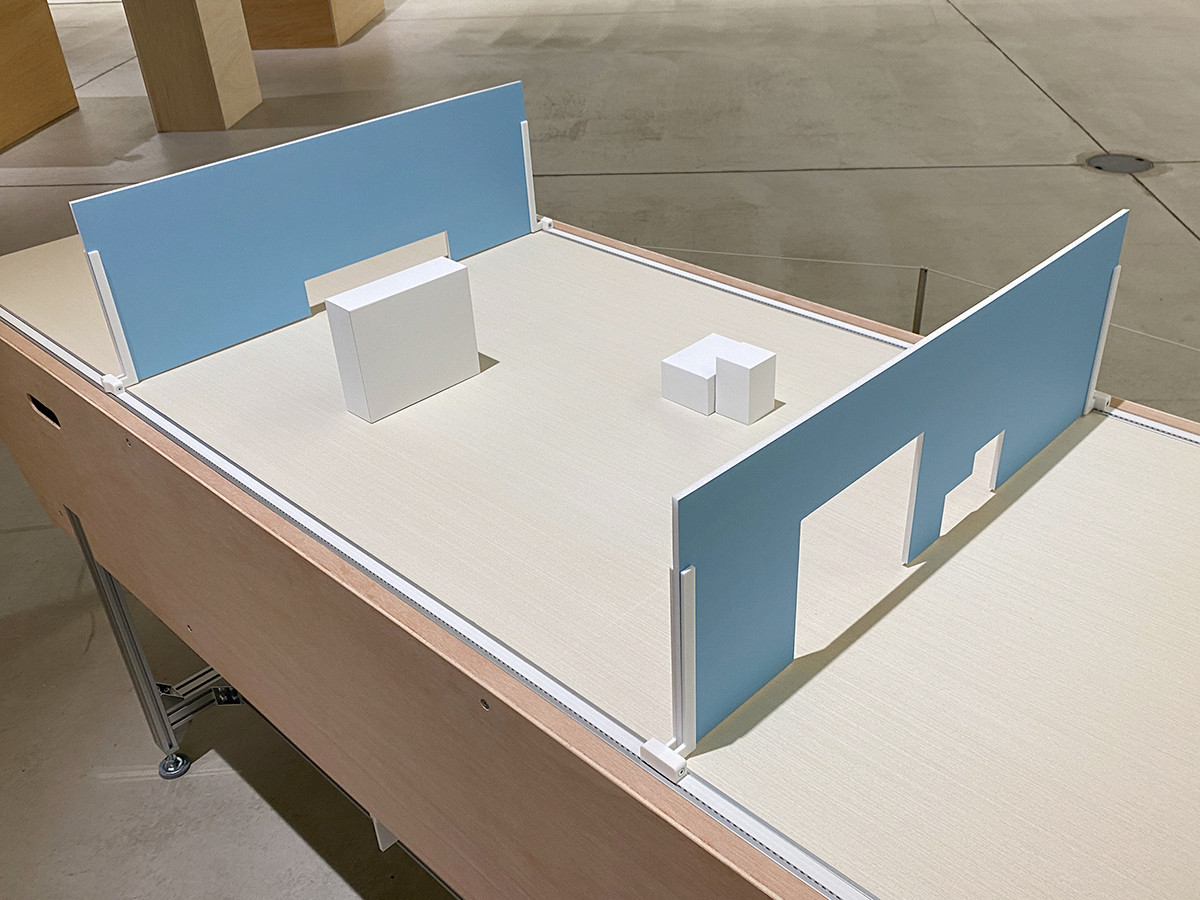IM
レポート
レポート
ルール?展
21_21 DESIGN SIGHT | 東京都
社会でともに生きるためのルールを、デザインでどのようにつくれるか?
会場に入る前に「鑑賞のルール」をスタンプで設定。ユニークなルールも
21_21らしい軽やかなアプローチながら、かなり考えさせられる展覧会です
3
「訓練されていない素人のための振付コンセプト003.1(コロナ改変ver.)」コンタクト・ゴンゾ
「滝ヶ原チキンビレジ」早稲田大学吉村靖孝研究室
「ひとりの髪を9人の美容師が切る(二度目の試み)」田中功起
「自分の所有物を街で購入する」丹羽良徳
| 会場 | 21_21 DESIGN SIGHT |
| 会期 |
2021年7月2日(金)〜11月28日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 平日 11:00 - 17:00、土日祝 11:00 - 18:00(入場は閉館の30分前まで) |
| 休館日 | 火曜日(11月23日は開館) |
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン |
| 電話 | 03-3475-2121 |
| 公式サイト | http://www.2121designsight.jp/ |
| 料金 | 一般1,200円、大学生800円、高校生500円、中学生以下無料 |
| 展覧会詳細 | 「ルール?」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年4月18日
横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入
2025年4月18日
日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」
2025年4月18日
開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」
2025年4月15日
ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集
[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)