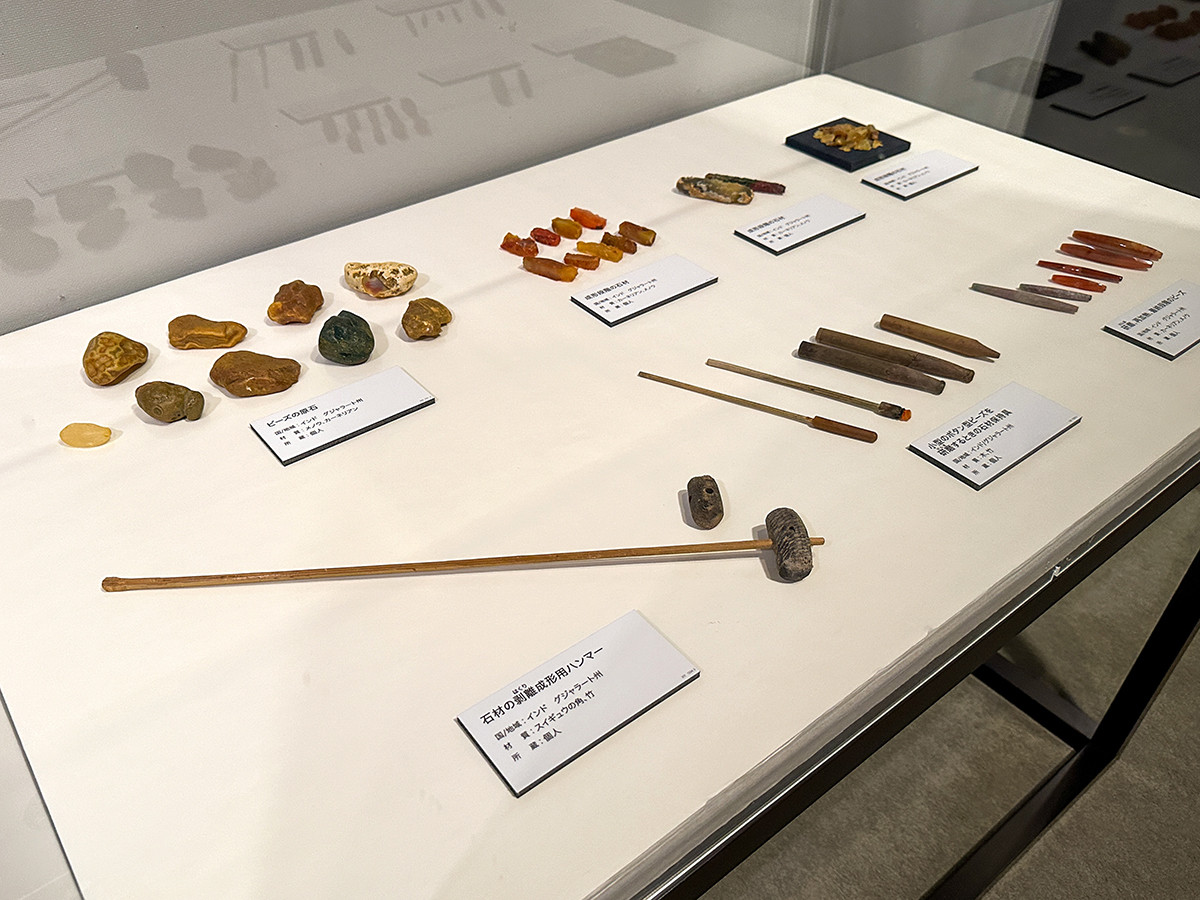IM
レポート
レポート
ビーズ ― つなぐ かざる みせる
渋谷区立松濤美術館 | 東京都
人類最古の装飾品のひとつ、ビーズ。一粒から無限に広がるその世界を展観
素材は土、石、ガラスと多様。植物の種、貝、動物の骨、人の歯もビーズに
世界各地で見られるビーズ。家族のつながり、民族のアイデンティティにも
4
「多様な素材 ツメ・ウロコ・骨」
「あゆみ 貝の道」《帽子》コンゴ民主共和国-国立民族学博物館
「あゆみ 貝の道」《戦闘用胸あて・胸あて・小手あて》インド-国立民族学博物館
「あゆみ 石の道」《腕飾り》アフガニスタン
「あゆみ 石の道」《頭飾り》インド
「つくる」《人像(ビーズ製)》ナイジェリア-国立民族学博物館
「ビーズで世界一周 東南アジア」
「ビーズ ― つなぐ かざる みせる」展 会場風景
| 会場 | 渋谷区立松濤美術館 |
| 会期 |
2022年11月15日(火)〜2023年1月15日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 特別展期間中:午前10時~午後6時(金曜のみ午後8時まで) 公募展・小中学生絵画展・サロン展期間中:午前9時~午後5時 最終入館はいずれも閉館30分前までです。 |
| 休館日 | 月曜日(ただし1月9日は除く)、11月24日(木)、12月29日(木)~1月3日(火)、1月10日(火) |
| 住所 | 〒150-0046 東京都渋谷区松濤2-14-14 |
| 電話 | 03-3465-9421 |
| 公式サイト | https://shoto-museum.jp/ |
| 料金 | 一般800円(640円)大学生640円(510円)、 高校生・60歳以上400円(320円)、小中学生100円(80円) *( )内は渋谷区民の入館料 *土・日曜日、祝休日は小中学生無料 *毎週金曜日は渋谷区民無料 *障がい者及び付添の方1名は無料 |
| 展覧会詳細 | 「ビーズ ― つなぐ かざる みせる」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年3月30日
明るく、楽しく、鑑賞しやすく。愛知県陶磁美術館がリニューアルオープンへ
2025年3月29日
二条城で出会う、キーファーの圧倒的スケール ― 「アンゼルム・キーファー:ソラリス」展
2025年3月28日
鳥取県立美術館がグランドオープン。記念展「ART OF THE REAL」も開催へ
2025年3月26日
過去・現在・未来を一挙公開! ― 「活動10周年記念 にしむらゆうじのひみつ展」
ご招待券プレゼント
学芸員募集
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
公益財団法人日本博物館協会 事業部門マネージャーの募集
[公益財団法人日本博物館協会]
東京都
東京国立博物館アソシエイトフェロー(日本考古/書跡・歴史資料)募集
[東京国立博物館(台東区上野公園13-9)]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)