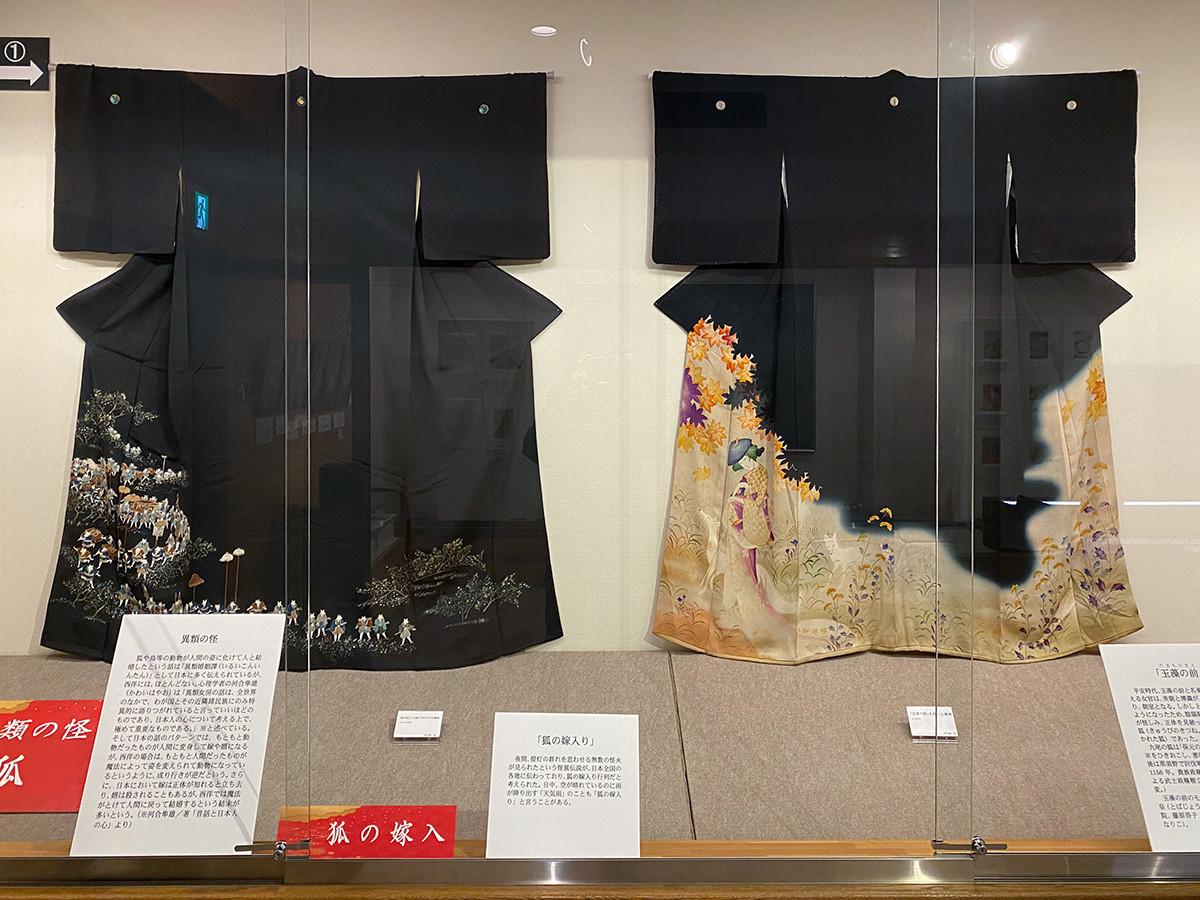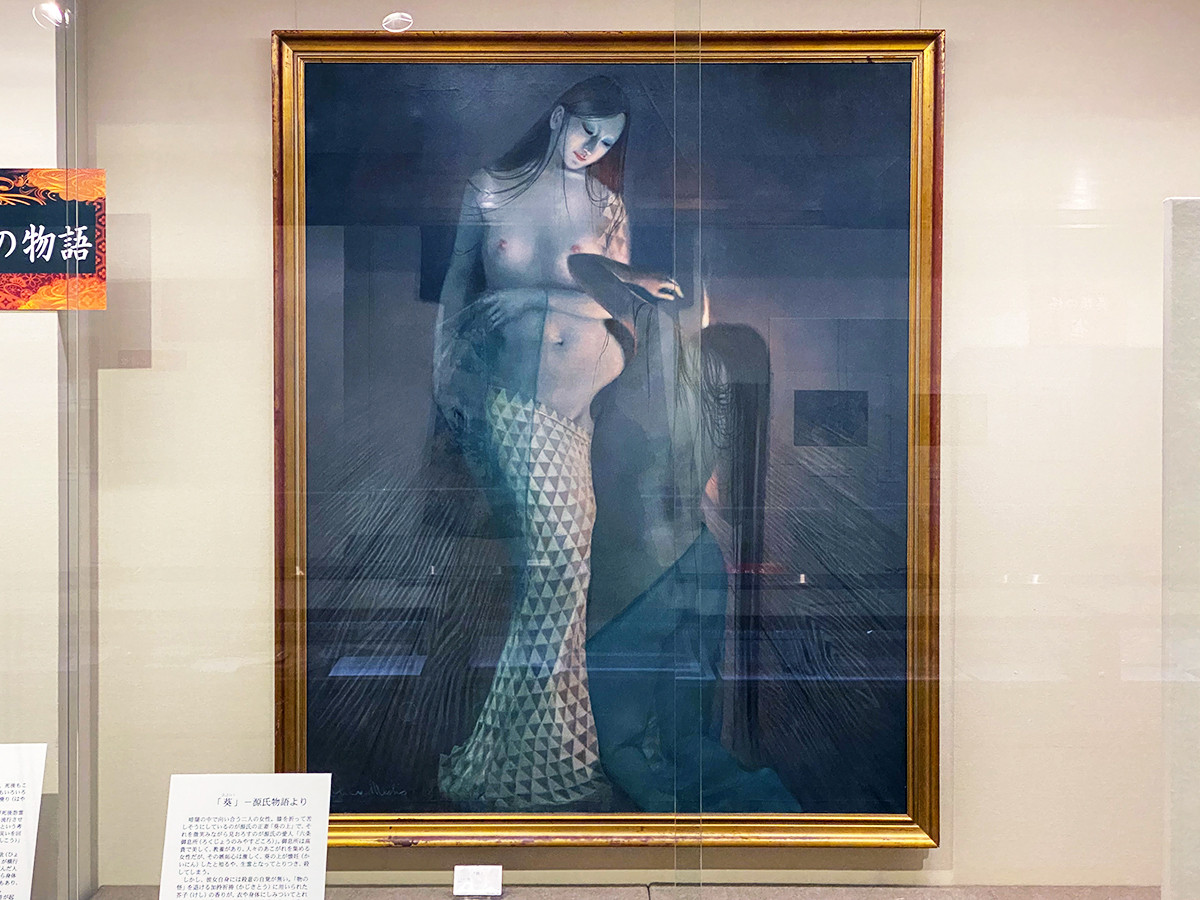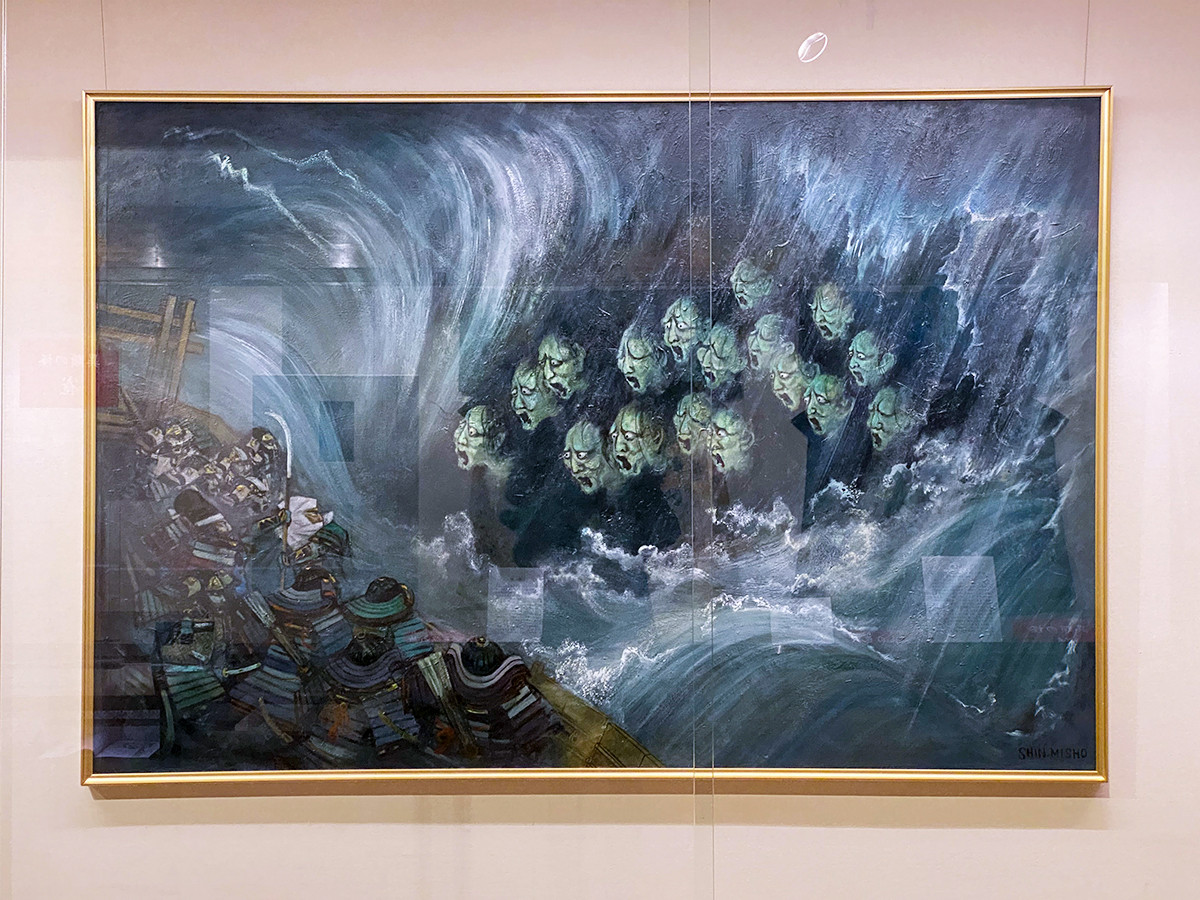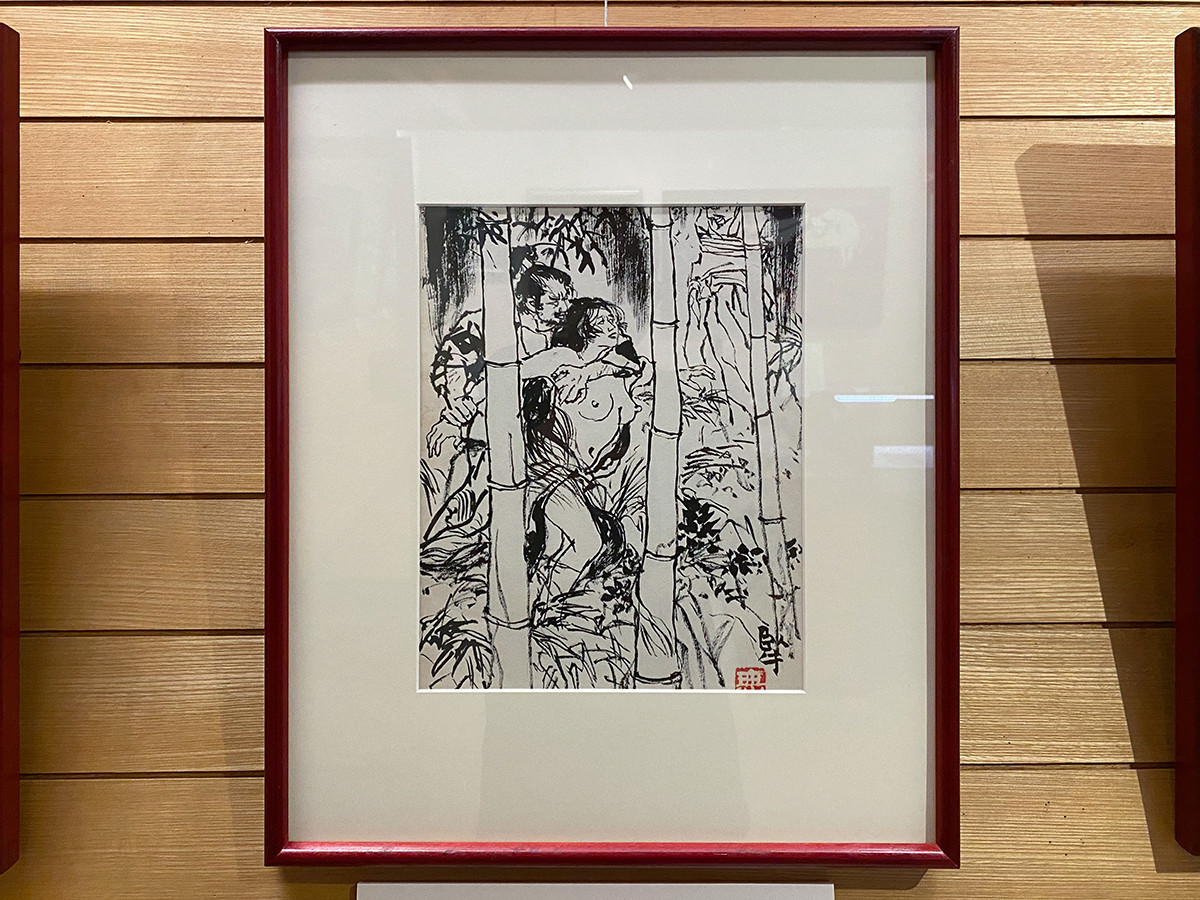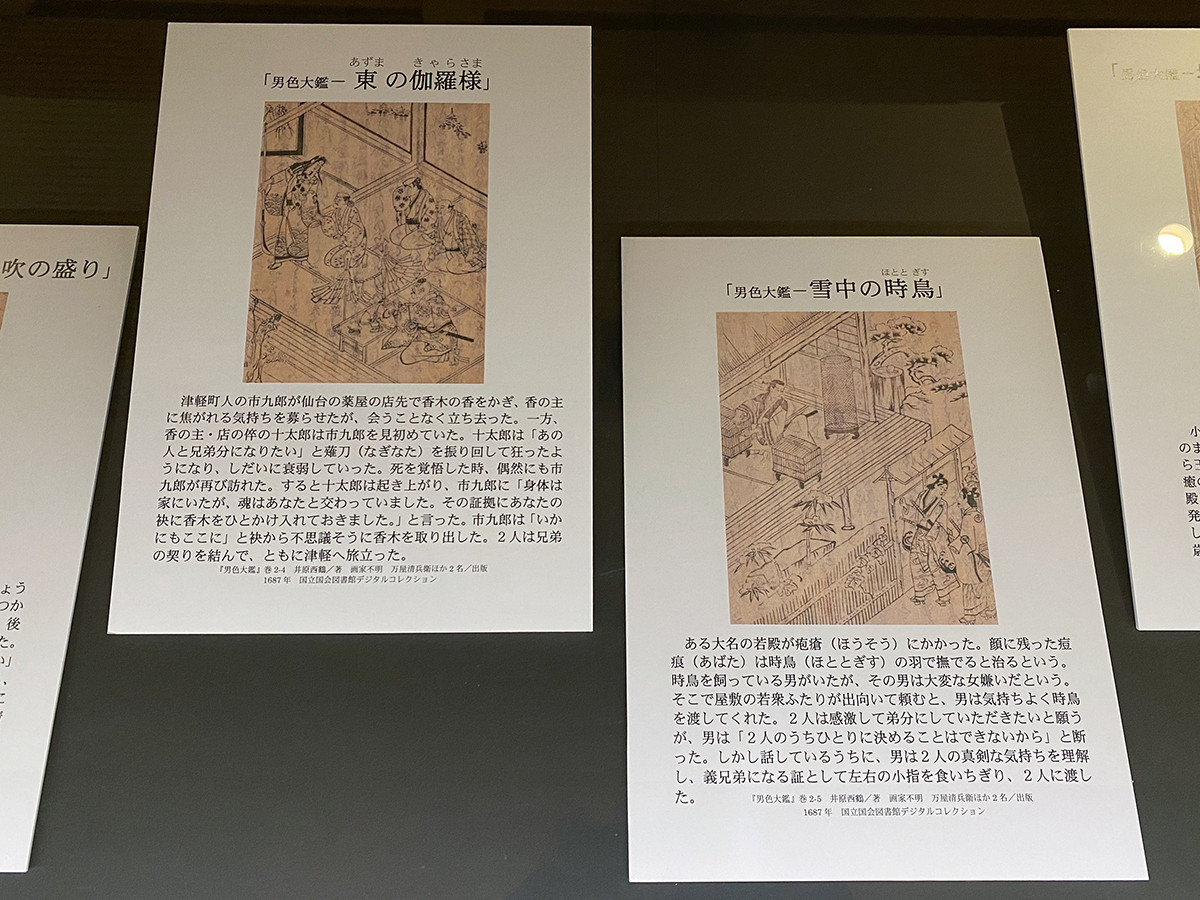IM
レポート
レポート
奇想の国の麗人たち
弥生美術館 | 東京都
長年語り続けられた伝説や古典文学を、物語にまつわる絵画とともに紹介
動物が人に化けて結婚する「異類婚姻譚」、生きている人から出た「生霊」
古典文学の一角を占めている男性同性愛も。欧米とは全く異なる倫理観
5
| 会場 | 弥生美術館 |
| 会期 |
2020年10月31日(土)〜2021年1月31日(日)
会期終了
|
| 開館時間 | 午前10時30分~午後4時30分 (入館は4時までにお願いします) |
| 休館日 | 月・火曜日 ※ただし11/3(祝火)、11/23(祝月)、1/11(祝月)開館、11/4(水)休館 年末年始(12/28~1/2) |
| 住所 | 〒113-0032 東京都文京区弥生2-4-3 |
| 電話 | 03-3812-0012 |
| 公式サイト | http://www.yayoi-yumeji-museum.jp/ |
| 料金 | 一般1000円/大・高生 900円/中・小生500円 (竹久夢二美術館もご覧いただけます) |
| 展覧会詳細 | 「奇想の国の麗人たち 」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2025年4月18日
横浜赤レンガ倉庫で線の魔術師・ミュシャの世界へ没入
2025年4月18日
日本美術の“交差点”をたどる特別展 ― 京都国立博物館「日本、美のるつぼ」
2025年4月18日
開館130年の奈良国立博物館で、過去最大規模の国宝展 ― 特別展「超 国宝」
2025年4月15日
ファッションに見る“私のかたち” ― 「LOVEファッション─私を着がえるとき」展
ご招待券プレゼント
学芸員募集
新居浜市美術館 学芸員募集中
[あかがねミュージアム(新居浜市美術館および新居浜市総合文化施設)]
愛媛県
東山旧岸邸 正社員・契約社員 募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
鎌倉 報国寺 学芸員募集(正職員)
[報国寺]
神奈川県
【新卒/経験者OK】都内環境啓発施設、常勤スタッフ(コーディネーター)募集中!
[武蔵野市環境啓発施設「むさしのエコreゾート」、エコギャラリー新宿(新宿区立環境学習情報センター・区民ギャラリー) など]
東京都
国分寺市 学芸員(埋蔵文化財担当)募集
[国分寺市教育委員会ふるさと文化財課]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)