IM
レポート
レポート
時空を超えた祈りのかたち ― 三井記念美術館「バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰」(レポート)
三井記念美術館 | 東京都
ガンダーラで生まれた弥勒信仰。中央アジアから中国・朝鮮を経て日本まで
タリバンにより破壊されたバーミヤン大仏壁画の描き起こし図が東京初公開
法隆寺など、日本の古寺に伝わる弥勒信仰の諸相も展示。京都からの巡回展
1
《仏伝浮彫「出城」》ガンダーラ・2~3世紀 半蔵門ミュージアム
《仏伝浮彫「初転法輪」》ガンダーラ・2~3世紀 東京国立博物館
《奉献小塔》ガンダーラ・2~3世紀 平山郁夫シルクロード美術館
《弥勒菩薩交脚像》ガンダーラ・2~3世紀 平山郁夫シルクロード美術館
《兜率天上の弥勒菩薩像》ガンダーラ・2~3世紀 東京国立博物館
《妙法蓮華経 巻第七 1巻》敦煌/唐・上元3年(676)三井記念美術館
| 会場 | 三井記念美術館 |
| 会期 |
2024年9月14日(土)〜11月12日(火)
会期終了
|
| 開館時間 | 10:00~17:00(入館は16:00まで) |
| 休館日 | 月曜日(月曜日が祝日・休日の場合は開館、翌平日が休館) 展示替期間、年末年始、臨時休館日 ※展覧会ごとの休館日は事前にご確認ください |
| 住所 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 三井本館7階 |
| 電話 | 050-5541-8600 (ハローダイヤル)
050-5541-8600
(ハローダイヤル)
|
| 公式サイト | https://www.mitsui-museum.jp/ |
| 展覧会詳細 | 「バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰」 詳細情報 |
おすすめレポート
ニュース
2026年1月5日
しょこたん大興奮!原画もグッズも集結 ─ 「リサとガスパール」25周年イベント
2025年12月26日
「昭和の春信」を総覧 ― あべのハルカス美術館で「密やかな美 小村雪岱のすべて」
2025年12月25日
新選組への商品代金の受領記録などが初公開 ― 高島屋史料館「タカシマヤ クロニクル」展
2025年12月24日
人気青春漫画『スキップとローファー』の展覧会がサンシャインで開催
ご招待券プレゼント
学芸員募集
歴史的建造物と庭園で働きたい方を募集!
[東山旧岸邸]
静岡県
阪神甲子園球場職員(歴史館担当)
[阪神甲子園球場(兵庫県西宮市、阪神電車「甲子園駅」徒歩3分)]
兵庫県
ほまれあ(三条市歴史民俗産業資料館別館)学芸員募集
[ほまれあ(三条市歴史民俗産業資料館別館)]
新潟県
KYOTOGRAPHIE京都国際写真祭2026 サポートスタッフ募集(ボランティア)
[京都文化博物館 別館、誉田屋源兵衛 竹院の間、京都市京セラ美術館 別本館 南回廊2階、Ygion、ASPHODEL、嶋臺ギャラリー、出町桝形商店街など [京都府]]
京都府
2026.4.1採用 国立新美術館 総務課研究補佐員(広報室)公募(2026年2月2日正午締切)
[国立新美術館]
東京都
おすすめコンテンツ
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)










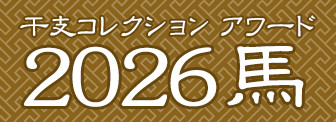

![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)