「博物館浴🄬(はくぶつかんよく)」という言葉を耳にしたことはありますか?
これは、森林浴や海水浴のように、博物館*などでの作品鑑賞を通して、ミュージアムの持つ癒し効果を人々の健康増進・維持や疾病予防に活用する活動です。
ミュージアムを「学びの場」とする、これまでの位置づけだけでなく、新たに健康・ウェルビーイングとしても活用できる施設として「博物館浴」を提唱している、九州産業大学 地域共創学部の緒方泉特任教授にお話を伺いました。
* 博物館法に基づき、歴史系・美術系・科学系などの施設を「博物館」と定義します。
■「博物館浴」に至るまでの経緯を教えてください
東京に生まれた私は、大学時代を過ごした京都で、さまざまな日本の文化に触れました。大友宗麟の菩提寺として建立された大徳寺 瑞峯院に下宿し、朝から掃除や修行、日本文化に深く浸る日々を送りました。
文学と歴史を学び、さらに心理学の博士号も取得し「歴史と心理を組み合わせてミュージアムを考える」という独自の視点が育まれていきました。
九州で就職した後、九州国立博物館の開館に関与することとなり、日本のミュージアムを調査するなかで気づいたことは、施設数の多さに比べて来館者が少ないという現実でした。
ミュージアムでは、作家や鑑賞者など『人』の心の動きが十分に発信されていないのではないか。心理学の観点から、ミュージアム内ではどういった心の動きがあるのか、海外の文献を調べるうちに至ったのが「博物館浴」です。

九州産業大学 地域共創学部の緒方泉特任教授
■今の日本のミュージアムの現状は?
日本には、博物系・美術系・科学系など5,700館ものミュージアムがあります。しかし、国民1人あたり、年間来館回数は、平均して2.1回といわれています。また「若者における美術館やアート全般に関する意識調査」では、美術館に全くいかない、無関心な若者が51.7%にのぼるという結果も出ています。
■海外の現状はどうですか?
たとえばイギリスでは「Museums Change Lives」と謳い、メンタルに課題を抱える子どもや若者にミュージアムは生活を変えてくれる場であることを伝えています。
実際、ロンドン大学の2019年研究では、文化芸術を鑑賞する機会の多い地域住民は、鑑賞する機会を全く持たない人に比べて死亡率が低かったというデータもあります。ミュージアムは、生活の質を高め、健康と福祉の施設と連携して、さまざまなニーズをもつ社会のさまざまな人々を支援しています。
2018年には、カナダの医師会から患者の健康回復を推進する治療の一環として、モントリオール美術館への訪問を「処方箋に書く」という実験的な取り組みもはじめられました。この取り組みは現在は、ベルギー、スイス、台湾にも広がっています。
■「博物館浴」の実証実験について教えてください
「博物館浴」の実験では、参加者に鑑賞前後で心理測定を行い、血圧や脈拍の変化などを記録します。データは即日で集計し、関係者へ速報値を提出する仕組みをとっています。
2020年9月からこれまで98館、延べ1,533人(中高生、大学生、社会人、高齢者など)を対象に「博物館浴」の実証実験をはじめています。
2024年6月には、国立西洋美術館で実施しました。静かな環境で個々に楽しむ「黙々鑑賞」の後、会話の中で鑑賞する「おしゃべり鑑賞」をすることによって数値は下がり、総合的な気分状態が良くなったことが分かりました。
■実証実験を行う上で、大切にしていることは何ですか?
はじめは、聞きなれない「博物館浴」に対して疑問に思われることもありますが、2つのことがポイントになっていると思います。1つ目、参加者の方は調査対象者でなく、ミュージアムを変えていくための共同研究者(リサーチパートナー)として参加していただいているということです。2つ目は、実験後に速報値と変化に対するコメントを報告することで、ミュージアム側がその成果や役立ちを実感しやすくなるという点です。

■ミュージアムが“居場所”にもなっているのですか?
福岡のある市で実施した実験では、学校には行けないが美術館なら行ける、という子どもが参加してくれました。美術館での鑑賞の際も、最初は下を向いて話せなかった子どもが、ノートに思いを書いてくれるようになり、好きな絵を探す活動を通して少しずつ変化していきました。血圧や脈拍の変化を本人が目の当たりにすることで、再訪にもつながりました。
■今後の展開を教えてください
今後は学校だけでなく、企業の健康経営との連携も視野に入れています。個人情報の扱いなどハードルはありますが、ストレスの多い現代社会においてミュージアムを新たなウェルビーイング資源として活用し、新たな健康ステーションのような役割を担っていけたらと考えています。
作品を観ることで、心と体が“ととのう”。「学びの場」や「静かな展示空間」として捉えられがちなミュージアムが、博物館浴によって心と身体を整える“ウェルビーイングの場”としての価値も期待されています。
これまでミュージアムに馴染みのなかった人たちにも、新しい扉を開いてくれるかもしれません。


「博物館浴🄬」のロゴマーク
![アイエム[インターネットミュージアム]](/_nuxt/img/logo-internet-museum.afe373c.svg)





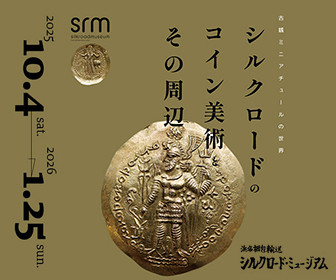


![デザイン情報サイト[JDN]](https://www.museum.or.jp/storage/article_objects/2025/07/23/a8d58cab781a.jpg)